
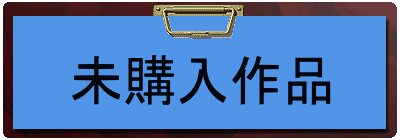
 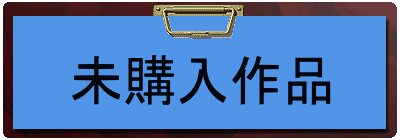 |
コード№別
▼ページの最後▼
| コードNo 95000 |
 |
| 95001(購入済) 734 |
「危険な広告」(1954年6月) |
| 95002(購入済) 736 |
「鮎返り」『地上』(1955年5月) |
| 95003(購入済) 709・709__02 |
「任務」(1955年12月) |
| 95004(購入済) 658 |
「炎風(信玄軍記)」※訂正(信玄戦旗」は間違い)(1956年3月) |
| 95005(し)(購入済) 659 |
「乱旗(信玄軍記)」※訂正(信玄戦旗」は間違い)(1956年4月) |
| 95006(購入済) 660 |
「陣火(信玄軍記)」※訂正(信玄戦旗」は間違い) (1956年5月) |
| 95007(購入済) 679 |
「栄落不測」(1956年4月) |
| 95008 | 「流れ路」『オール讀物』(1956年11月) |
| 95009 | 「いたち党」『朝日新聞ジュニア版』(1957年3月14日~9月5日)未完 |
| 95010(購入済) 617 |
「八十通の遺書」(1957年4月) |
| 95011(購入済) 738 |
「悲運の落手」(1957年5月~6月) |
| 95012(購入済) 681 |
「亀五郎犯罪誌」(1957年8月) |
| 95013(購入済) 735 |
「筆記原稿」(1957年9月) |
| 95014(い) | 戯曲■「いびき地獄(戯曲)」(1957年12月) ※戯曲 |
| 95015 | 「虚線」(1958年1月~2月) (休刊のため中絶)「零の焦点」として宝石に再掲載 |
| 95016 | 「旅先」『新潮』(1956年8月) |
| 95017(ふ) | 座談会■「部落問題と文学<座談会=、吉見扛児、開高健、杉浦明平、野間宏>」(1959年2月) ※座談会 |
| 95018 | 「火の前夜」『別冊週刊サンケイ』(1959年5月~9月) |
| 95019(く) | 私の発想法--黒い色感から(インタビュー・葉)『朝日ジャーナル・創刊号』(1959年3月15日) |
| 95020(れ) | 座談会■歴史文学をめぐって<座談会=桑田忠親、佐治芳雄、進士慶幹、黒板拡子、児玉幸多、田中健夫、岡田章雄、松本清張> 『日本歴史』(1957年1月~2月) ※座談会 |
| 95021 | わたしの古典『日本読書新聞』(1958年11月3日) |
| 95022(購入済) 711 |
「陽炎」『暁鐘』(1951年10月10日) 再録/「月刊はかた」 |
| 95023 | 作者の言葉(家康と山師)『代表作時代小説 昭和三十年度』〔東京文藝社〕(1955年10月10日) |
| 95024 | 作者の言葉(ひとりの武将)『代表作時代小説 昭和三十一年度』〔東京文藝社〕(1956年10月25日) |
| 95025 | 作者の言葉(いびき)『代表作時代小説 昭和三十二年度』〔東京文藝社〕(1957年9月25日) |
| 95026(け) | アンケート■アンケート・アンケート回答(現代・歴史的仮名づかい)『知性』(1955年10月) ※アンケート |
| 95027 | あとがき■あとがき(腹中の敵)『時代小説集一』軽文学新書、鱒書房(1955年7月) |
| 95028 | あとがき■あとがき『悪魔に求める女』コバルト新書、鱒書房(1955年8月) |
| 95029 | あとがき■あとがき『風雪』角川小説新書(1956年11月) |
| 95030 | あとがき■あとがき『点と線』光文社(1958年2月) |
| 95031 | あとがき■あとがき『眼の壁』光文社(1958年2月) |
| 95032 | あとがき■あとがき『推理小説作法』光文社(1958年4月) |
| 95033 | あとがき■あとがき『黒地の絵』光文社(1958年6月) |
| 95034 | 「永仁の壺」『芸術新潮』(1959年9月) |
| 95035(か) | 鴎外の暗示『文芸推理小説選集一 森鴎外・松本清張集』〔文芸評論社〕(1957年2月) 解説に代えて ※解説 |
| 95036(し) | 大井広介『英雄よみがえる』書評『図書新聞』(1958年4月5日) ※書評 |
| 95037 | 教えた誤字『東京新聞』(1956年9月18日) |
| 95038 | 閑暇を楽しむ『新刊ニュース』(1958年5月) ※読み=閑暇(カンカ) |
| 95039 | 「菊枕」について石氏へ〔文藝春秋〕(1953年10月) |
| 95040 | 期待はずれの労作『日本読書新聞』(1958年9月9日) |
| 95041 | 九州の隠された旅館から--歴史小説のみた風物のかずかず(文・画)『旅』(1954年12月) |
| 95042 | 偶像化へのいましめ『淡交』(1957年10月) |
| 95043(こ) | 決戦川中島『決戦川中島 少年少女歴史小説全集十二』 この本を読む皆さんへ 〔大日本雄弁会講談社〕(1957年11月25日) 決戦川中島・燃える陣火 |
| 95044 | 梗概に代えて(大奥婦女記)『新婦人』(1956年4月~11月) |
| 95045 | 後記『小説日本芸譚』『新潮社』(1958年6月) |
| 95046 | 高原と温泉の九州旅行『旅』(1956年3月) |
| 95047 | 荒天の舟出 芥川賞昭和二十七年度『新潮』(1956年3月) |
| 95048 | 小倉城(福岡県北九州市)少年の頃『週刊読売』(1955年) 〔再録〕『古城にうたう』〔鹿島研究所出版会〕(1966年5月) |
| 95049 | この小説集について『空白の青春』帯、有馬頼義著 〔作品社〕(1956年10月) |
| 95050 | この伝記を読む人に『徳川家康』〔大日本雄弁講談社〕(1955年4月) |
| 95051 | 五味康祐(百人百説 現代作家読本--一九五五年の横顔)『文藝』(1955年12月) |
| 95052 | 私注--「小倉日記」妙『鴎外全集 著作編二五 月報』〔岩波書店〕(1953年6月10日) |
| 95053 | 書斎めぐり『図書新聞(376)』(1956年12月1日) |
| 95054(し) | 座談会■勝負師群像--乱世の処世哲学<座談会=中山義秀、榊山潤、大井廣介、松本清張>『特集文藝』(1956年12月) ※座談会 |
| 95055 | 新聞の谷間『共同配信』(1958年10月1日) |
| 95056 | 資料ばなし 面・白・い・野・史・俗・書--殺すも生かすも作家の眼『図書新聞』(1956年1月1日) |
| 95057 | 時刻表と絵葉書『旅』(1956年9月) |
| 95058 | 推理小説に知性を『東京タイムス』(1958年3月17日) |
| 95059 | 推理小説の独創性『東京新聞・夕刊』(1958年3月26日) |
| 95060 | スリラー映画・何故つまらない『藝術新潮9(3)』(1958年3月1日) |
| 95061 | 第一回朝日文芸入選の感想『朝日新聞』(1951年3月15日) |
| 95062 | 確かな歴史小説 南条範夫著『燈台鬼』『図書新聞(365)』(1956年9月15日) |
| 95063 | 楽しい謎とき『週刊文春』(1959年6月1日) |
| 95064 | 著者のことば『悪魔にもとめる女』〔コバルト新書/鱒書房〕(1955年8月30日) |
| 95065 | 角田さんの受賞『日本探偵作家クラブ会報』(1958年4月) |
| 95066 | 動機を追求す『日本探偵クラブ会報』(1957年10月) |
| 95067 | 読書的回想『探偵小説名作全集九 坂口安吾・蒼井雄集・月報』〔河出書房〕(1956年8月31日) |
| 95068(と) | 対談■殿方ご用心遊ばせ<対談・佐藤みどり>『中央公論』(1958年7月) ※対談 |
| 95069(む) =401(原題) |
「なかま」●《改題=雨と川の音》「雨と川の音」の前編となる。(1958年7月) |
| 95070(な) | 対談■なんともうしましょうか<対談・小西得郎>『週刊漫画TIME』(1958年11月19日) ※対談 |
| 95071(む・る) =398(原題) |
「抜け舟」(【無宿人別帳】第八話)●《改題=「流人騒ぎ」》「流人騒ぎ」の後編となる。(1958年7月) |
| 95072 | 「猫は知っていた」書評『読書新聞』(1957年12月2日) |
| 95073 | 批評『三田文学』(1955年10月) |
| 95074 | 100番目にこれを推す『日本読書新聞』(1959年3月16日) |
| 95075(購入済) 715 |
ひとり旅(エッセイ文・画)『旅』(1955年4月) |
| 95076 | ブームの眼の中で『QMM』 (1958年6月) |
| 95077 | 三河気質『小説春秋』(1956年12月) |
| 95078(め) | 対談■名将・知将・勇将を語る<対談・尾崎士郎>『「キング』(1956年2月) ※対談 |
| 95079 | 略歴『年刊日本文学昭和二十七年度』(1953年4月10日) |
| 95080 | 歴史小説寸感『奥羽の二人』〔和光堂〕(1954年8月5日) |
| 95081(購入済) 737 |
「女に憑かれた男」〔小説春秋〕(1956年8月5日) |
▲ページのTOP▲ ●95000●96000●97000●98000●99000●不明 ▼ページの最後▼
| コードNo 96000 |
 |
| 96001(購入済) 739 |
「秘壺」(1960年9月) |
| 96002(購入済) 680 |
「草笛」(1960年9月) |
| 96003(購入済) 740 |
「電筆」(1961年1月) |
| 96004 | 「水の中の顔」『週刊朝日別冊』(1961年1月) |
| 96005(購入済) 656 |
「偶数」『小説新潮』(1961年2月) |
| 96006(購入済) 612 |
「よごれた虹」(1962年11月) |
| 96007(購入済) 730 |
「暗色調(ダークトーン)の中の風景」『女性自身・増刊号』(1962年11月) |
| 96009 | 「甃」『女性自身』(1964年6月15~12月21日) ※読み=(イシダタミ) |
| 96010(購入済) 678 |
「泥炭層」(1965年12月) |
| 96011 | 「狩猟」『オール讀物』(1966年1月~1967年1月) |
| 96012 | 「雨」『別冊宝石』(1966年8月) 【同姓同名】 |
| 96013 | 「東風西風」『讀賣新聞/夕刊』(1967年7月3日~1968年6月28日) |
| 96014 | 「地を匍う翼」『別冊文藝春秋』(1967年12月) ※読み=チヲハウツバサ |
| 96015-00(ま) | 対談■「松本清張対談」(1968年1月~1968年12月) ※対談 |
| 96015-01(や) | 対談■「やんちゃ皇族の戦争と平和<対談・東久邇稔彦>」『松本清張対談・文藝春秋』(1968年2月) ※対談 |
| 96015-02(せ)(購入済) 742-02 |
対談■「戦争と貧困はなくせるか<対談・池田大作>」『松本清張対談・文藝春秋』(1968年2月) ※対談 |
| 96015-03(き) | 対談■「キューバ・佐世保・ベトナム<対談・大森実>」『松本清張対談・文藝春秋』(1968年3月) ※対談 |
| 96015-04(と) | 対談■都政ただいま体質改善<対談・美濃部亮吉> 『松本清張対談・文藝春秋』(1968年4月) ※対談 |
| 96015-07(さ) | 対談■最後の元老西園寺公の素顔<対談・橋本実斐> 『松本清張対談・文藝春秋』(1968年4月) ※対談 |
| 96015-08(き) | 対談■「騎馬民族が日本を征服した<対談・江上波夫>」『松本清張対談・文藝春秋』(1968年8月) ※対談 |
| 96015-09(い) | 対談■医者に博士号はいらない<対談・中山恒明> 『松本清張対談・文藝春秋』(1968年10月) ※対談 |
| 96015-10(め) | 対談■明治は日本のルネッサンス<対談・桑原武夫> 『松本清張対談・文藝春秋』(1968年11月) ※対談 |
| 96015-11(け) | 対談■経営とは傘をさすことなり<対談・松下幸之助> 『松本清張対談・文藝春秋』(1968年12月) ※対談 |
| 96016 | 「「中国と北ベトナムはどう出るか」」(1968年6月) |
| 96017(購入済) 616 |
「山」(1968年7月) |
| 96018 | 「再説・下山国鉄総裁謀殺論」(1969年8月) |
| 96019 | 「石」『小説宝石』(1969年12月~1970年5月) |
| 96020(し) | 対談■私小説と本格小説<対談・平野謙>『群像』(1962年6月) ※対談 |
| 96021(え) | 偉大なる作家江戸川乱歩『別冊宝石』(1962年2月) |
| 96022 | 一冊の本『朝日新聞』(1960年11月2日) |
| 96023 | 「移りゆく武蔵野」『朝日新聞』(1961年9月10日) |
| 96024(え) | 解説■江戸川乱歩『日本推理小説大系二』(解説)〔東都書房〕(1960年4月) ※解説 |
| 96025 | 落葉『朝日新聞』(1963年12月9日) |
| 96026(お) | 戯曲■鬼三味線(戯曲)「読売ホールにて上演」(1963年7月) ※戯曲 |
| 96027 | 解説■解説・責任監修『書き下ろし新本格推理小説全集 全十巻』〔読売新聞社〕(1966年12月) ※解説 |
| 96028(さ) | 回想「酸素テントの中の格闘」『週刊新潮』(1968年8月31日) |
| 96029 | 書いたころ『松本清張短編総集』〔講談社〕(1963年4月10日) |
| 96030 | 新しい推理小説『讀賣新聞』(1966年12月19日) |
| 96031 | あの頃の自分のこと『オール讀物』(1962年6月) |
| 96032 | あとがき■あとがき『現代人の日本史十七 幕末の動乱』〔河出書房新社〕(1961年5月) |
| 96033 | あとがき■あとがきに代えて『深層海流』〔文藝春秋新社〕(1962年12月) |
| 96034 | あとがき■あとがき『松本清張短編全集3 張込み』〔カッパ・ノベルス/光文社〕(1964年1月) |
| 96035 | あとがき■あとがき『松本清張短編全集8 遠くからの声』〔カッパ・ノベルス/光文社〕(1964年10月) |
| 96036 | あとがき■あとがき『松本清張短編全集9 誤差』〔カッパ・ノベルス/光文社〕(1964年11月) |
| 96037 | あとがき■あとがき『松本清張短編全集10 空白の意匠』〔カッパ・ノベルス/光文社〕(1964年12月) |
| 96038 | あとがき■あとがき『松本清張短編全集11 共犯者』〔カッパ・ノベルス/光文社〕(1965年2月) |
| 96039 | あとがき■あとがき『天保図録 下』〔朝日新聞社〕(1965年2月) |
| 96040(購入済) 814 |
あとがき■あとがき『半生の記』〔河出書房新社〕(1966年10月) |
| 96041(購入済) 243 |
あとがき■あとがき『ハノイで見たこと』『朝日新聞』(1968年8月20日) |
| 96042(購入済) 807 |
あとがき■あとがき『小説東京帝国大学』〔新潮社〕(1969年12月) |
| 96043(わ) | カイロ--口にのぞく貧しさ『私の旅情』〔毎日新聞社/外信部編〕(1965年4月) |
| 96044 | 岸田劉生への疑問『藝術新潮・12(1)』(1961年1月) |
| 96045 | 紀勢での感動と失望『旅』(1961年2月19日) |
| 96046 | 木々先生のこと『宝石』(1962年4月) |
| 96047(け) | 座談会■現代の文学と大衆(座談会・川端康成、丹波文雄、円地文子、井上靖、三島由紀夫、松本清張>『文藝』(1963年5月) ※座談会 |
| 96048 | 警察と犯罪捜査『讀賣新聞』(1963年5月10日) |
| 96049 | 警視庁捜査二課『朝日新聞』(1961年8月2日) |
| 96050 | 懸賞小説に期待する『朝日新聞』(1963年3月23日) |
| 96051 | 現代社会の歪み「差別」『部落18(2』(1966年2月) |
| 96052 | 現代日本の差別『部落・臨時増刊20(11)』(1968年9月) |
| 96053 | 古代出雲の王権は存在したか(共同討議=門脇禎二、佐原真、近藤喬一、速水保孝、司会/松本清張)『銅剣・銅鐸・銅矛と出雲王国の時代』 〔日本放送出版協会〕(1968年9月20日) |
| 96054 | 「こぐり」の味『讀賣新聞』(1962年1月1日) |
| 96055 | このごろ『朝日新聞』(1964年11月5日) |
| 96056 | こわもて『毎日新聞/夕刊』(1962年3月3日) |
| 96057 | 私の本だな『東京新聞』(1965年3月27日) |
| 96058 | 作者の言葉(水の中の顔)『代表作時代小説 昭和三十六年度』〔東京文藝社〕(1961年9月) |
| 96059(さ) | 対談■三億円犯人との対話<対談・南博>特集・一九六九年・8つのポイント『潮』(106)(1969年2月) ※対談 |
| 96060 | 作家の内的衝動『日本近代文学館設立趣意二』(1963年11月) |
| 96061 | 作家論『坂口安吾全集八』〔冬樹社〕(1969年10月) |
| 96062(お) | 対談■女に振られる暇もない<対談・岡部冬彦>『週刊公論』(1961年5月22日) ※対談 |
| 96063=328(き) | (【現代官僚論】第六話)「旧内務官僚論」(1964年1月)」 |
| 96064=329 | (【現代官僚論】第七話)「建設官僚論」(1964年2月) |
| 96065=332(ほ) | (【現代官僚論】第十話)「防衛官僚論」(1964年9月~11月) |
| 96066=333(う) | (【現代官僚論】第十一話)「運輸官僚論」(1965年1月~3月) |
| 96067=334(お) | (【現代官僚論】第十二話)「大蔵官僚論』(1965年5月・6月・8月・9月) |
| 96068=335(か) | (【現代官僚論】第十三話)「外務官僚論」(1965年10月・11月) |
| 96069=356(せ)(購入済) 356 |
(【昭和史発掘】第十六話)「政治の妖雲・隠田の行者」(1966年12月12日~1967年1月16日) |
| 96070=358(お)(購入済) 358 |
(【昭和史発掘】第十八話)「「お鯉」事件」(1967年4月10日~5月15日) |
| 96071 | 下山事件「自殺論」について『赤旗』(1969年7月5日) |
| 96072 | 「下山事件」追跡の手を止めるな!『週刊朝日』(1964年7月10日) |
| 96073 | 集落(詩)『風景』(1963年3月) |
| 96074(か) | 序『カッパ大将--神吉晴夫奮戦記』片柳忠男著〔オリオン出版部〕(1962年9月25日) |
| 96075(に) | 序『日本推理小説年鑑 一九六四年版推理小説ベスト二四』〔東都書房〕(1964年6月) |
| 96076 | 『小説研究一六講』を読んだ頃『朝日新聞』(1960年11月2日) |
| 96077 | 小説のための地方色メモ『旅』(1960年6月) |
| 96078 | 私立探偵社『朝日新聞』(1961年3月26日) |
| 96079 | 深夜租界『朝日新聞・夕刊』(1961年1月8日) |
| 96080(す) | 座談会■推理小説の作者と読者<座談会=水沢周、高木彬光、松本清張>『思想の科学(7)』(1962年10月) ※座談会 |
| 96081=726(す)(購入済) 726 |
推理小説の文章『推理小説入門』〔光文社〕(1960年3月) |
| 96082 | 砂の国の苦悩『讀賣新聞』(1967年5月) |
| 96083(す) | 対談■推理を呼ぶもの<対談・戸板康二>『放送朝日』(1963年1月) ※対談 |
| 96084 | 選考経過報告(江戸川乱歩賞選考委員)『高層の死角』森村誠一著 〔講談社〕(1969年8月) |
| 96085 | 占領「鹿鳴館」の女たち『婦人公論』(1960年11月) |
| 96086(め) | 私はこの時代に生きたかった 明治時代(特撮グラビア)『別冊宝石』(1966年8月) |
| 96087 | 創作「ヒント帖」から『別冊小説新潮』(1961年10月) |
| 96088(そ・ほ) | 追悼&弔詞■その人柄を偲ぶ(ホー・チ・ミン主席を追悼する)『文化評論(98)』(1969年11月) ※追悼&弔辞 |
| 96089(て) | 対談■対談・鼎談『保存版・司馬遼太郎の世紀』斉藤禎爾・責任編集 〔朝日出版〕(1969年6月25日) ※対談・鼎談 <出席者=島尾敏雄・桑原武夫・橋川文三・武田泰淳・花田清輝・松本清張> |
| 96090 | 大臣のイス『朝日新聞』(1966年8月8日) |
| 96091(た) | 追悼&弔詞■多佳子月光(追悼・橋本多佳子)『俳句12(8)』(1963年8月) ※追悼&弔辞 |
| 96092=202(た) | 「【ミステリーの系譜】第二話『脱獄』」『週刊読売』(1967年10月20日~11月17日) |
| 96093(た) | 父から娘へ<対談・井上靖>『若い女性』(1961年5月) ※対談 |
| 96094 | 鳥海青児自選展『朝日新聞』(1962年10月12日) |
| 96095 | 著者のことば『今日の風土記』〔カッパ・ビブリア/光文社〕(1966年3月~1967年8月) |
| 96096 | 東京・水上暑『朝日新聞』(1961年5月14日) |
| 96097 | 泥の中の「佐野乾山」『術新潮13(10)』(1962年10月1日) |
| 96098=205(な) | 「【ミステリーの系譜】第五話『夏夜の連続殺人事件』」『週刊読売』(1968年2月23日~4月5日) |
| 96099-00 | 『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96099-01(購入済) 674 |
『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96099-02(購入済) 672 |
『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96099-03(購入済) 671 |
『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96099-04(購入済) 675 |
『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩の旅 |
| 96099-05(購入済) 673 |
『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96099-06 | 『今日の風土記』全六巻、共著・樋口清之〔光文社文庫/光文社〕(1966年3月~1967年8月) 付・著書のことば--こんな念願で、『今日の風土記』を書いた。 〔細目〕〕(一)京都の旅(1)/(二)奈良の旅/(三)東京の旅/(四)京都の旅(2)/(五)鎌倉(箱根・伊豆)の旅/ (6)南紀(伊勢志摩)の旅 |
| 96100 | 日本考古展を見て『朝日新聞・夕刊』(1969年11月17日) |
| 96101(け) | 幕末の動乱『現代人の日本史第十七巻 幕末の動乱』〔河出書房新社〕(1961年5月1日) 付・あとがき |
| 96102 | 二十歳のころ『讀賣新聞社・夕刊』(1969年1月6日) |
| 96103 | 母親運動の統一を喜ぶ『文化評論」(72)』(1967年10月)第十三回日本母親大会全体会講演 ※講演 |
| 96104 | 林房雄氏の文芸時評について『朝日新聞』(1963年6月7日) |
| 96105 | 林房雄氏の回答に寄す『朝日新聞』(1963年6月25日) |
| 96106(こ)(ま) | 判決をめぐって--国民と裁判(松川判決をめぐって)『世界(190)』(1961年10月) |
| 96107 | ひとつの敵は本能寺にあり--部落問題『日本読書新聞』(1961年12月4日) |
| 96108 | 平林たい子さんに訊く『読書新聞』(1962年10月22日) |
| 96109(ひ)(購入済) 710 |
追悼&弔詞■広津氏と「松川裁判」(広津和郎氏追悼)『文藝7(8)』(1968年11月) ※追悼&弔辞 ※松川裁判の「愉しみ」 追悼:広津和郎 |
| 96110 | 再び平林たい子さんに訊く『読書新聞』(1962年11月12日) |
| 96111 | 再び山本謙吉氏へ『讀賣新聞』(1967年8月23日) |
| 96112 | 古い小倉の町『讀賣新聞・夕刊』(1963年3月12日) |
| 96113(け) | 編集委員『現代長篇推理小説全集』(全十六巻)〔東都書房〕(1962年7月~1963年11月) |
| 96114(ほ) | 戯曲■細川の茶碗(1964年12月)(新橋演舞場/前進座のために執筆された) ※戯曲 |
| 96115 | 牧逸馬と私『一人三人全集 林不忘・谷謙次・牧逸馬集』〔河出書房新社〕(1969年11月) |
| 96116 | 松川裁判の「愉しみ」(特集・広津和郎)『群像23(12)』(1968年12月) |
| 96117 | 名作取材紀行『ゼロの焦点』『週間読書人』(1962年1月20日) |
| 96118(め) | 座談会■明治維新の志士たち<座談会=小西四郎、津久井龍雄、松本清張・司会/池島)『歴史よもやま話・日本編下』池島信平編〔文藝春秋〕 (1966年8月1日) NHK放送日1961年10月19日 ※座談会 |
| 96119(も) | 講演■木綿餅の絵『統合記念天神島』(北九州天神島小学校)(1968年) ※講演 |
| 96120(や) | 対談■やァこんにちは<対談・近藤日出造>『週刊読売』(1962年6月3日) ※対談 |
| 96121(や) | 対談■やァこんにちは<対談・近藤日出造>『週刊読売』(1966年12月9日) ※対談 |
| 96122 | 「邪馬台国」に対話を『朝日新聞』(1967年3月7日) |
| 96123 | 山本謙吉氏の「火の虚舟」について『讀賣新聞』(1967年8月8日) |
| 96124(ゆ) | 戯曲■遊殺「宝塚劇団によって明治座にて上演」(1963年)11月 ※戯曲 |
| 96125(れ) | 対談■歴史作家の感覚<対談・永井路子>〔対談グラビア〕先進後進 『朝日ジャーナル』(1966年4月4日) ※対談 |
| 96126 | ロマンチズムの発掘〔改題〕 『現代ノンフィクション全集二』筑摩書房(1968年1月) |
| 96127 | わが小説--「断碑」『朝日新聞』(1961年11月17日) |
| 96128(つ) | わが理想の人『角田久喜雄氏華甲記念文集』〔角田喜久雄文集編集委員会〕(1966年5月) |
| 96129 | 私の周辺『毎日新聞』(1962年2月1日) |
▲ページのTOP▲ ●95000●96000●97000●98000●99000●不明 ▼ページの最後▼
| コードNo 97000 |
 |
| 97001(こ)(改題) | 対談■「古代史の謎一 <対談=水野祐>」『赤旗』●原題=古代史の謎 (1970年1月1日~24日) ※対談 |
| 97002(こ) | 「対談のあと--「古代史の謎」の連載を終わって」 (1970年1月25日) |
| 97003(こ)(改題) | 対談■「古代日本人の生活をめぐって<対談・藤間生大>●原題=古代史の謎を探る (1972年6月) ※対談 |
| 97004(こ・そ)(改題) | 対談■「古代史の謎二 <対談・和歌森太郎>」●原題=続 古代史の謎 (1970年4月15日~5月13日) ※対談 |
| 97005 | 「新解釈・魏志倭人伝」(1970年5月)(未完) |
| 97006 | 「古代史の謎」『週刊読売』(1979年5月6日13日・27日) (97001=『赤旗』(1970年1月1日~24日)とは別) |
| 97007(こ) | 対談■「古代史の謎三 大王への道<対談・井上光貞>」(1970年10月18日~11月24日) ※対談 |
| 97008 | 「私の教科書批判--歴史」(1970年11月23日~1971年3月8日) |
| 97009(改題)(購入済) 743 |
「遊古疑考」『藝術新潮』●原題=遊史疑考(1971年1月~1972年11月) |
| 97010(や)(原題) | 「日本の古代国家-邪馬台国の謎を探る」(1971年7月) |
| 97011(に) | 戯曲■北一輝の・・・▼「日本改造法案-北一輝の死(戯曲)」(1972年5月) ※戯曲 |
| 97012(こ)(改題) | 座談会■「古代日本人の生活をめぐって<座談会=和島誠一、甘粕健、松本清張>(1972年6月)●原題=古代史の謎を探る ※座談会 |
| 97013(ふ) | 対談■「文壇の”社会派”大いに語る<対談・石川達三>」(1973年2月) ※対談 |
| ■古代史■ 97014 (購入済) 708 (改題) |
「古事記の機能」●原題=古事記の謎を探る(1973年6月12日) |
| 97015(購入済) 613 |
「河西電気出張所」(1974年1月) |
| 97016 | 「疑通史-古代信仰は日本固有のものか」(1974年1月) |
| 97017 | 「トンニャット・ホテルの客」『野性時代』(1974年5・6・8月) |
| 97018 | 「雨」『別冊文藝春秋128』(1974年6月) 【同姓同名】 |
| 97019 | 「公木元生氏の口舌--ある小説家の北陸路講演」(1974年12月) |
| 97020 | 対談■大推理3億円事件と連続爆破事件<特別対談・立花隆>『週刊文春』(1975年11月20日) ※対談 |
| 97021(購入済) 751 |
座談会(シンポジュウム)■「ヤマタイ国-わが内なる国家と民族」 出席者(藤間生大、上田正昭、田辺昭三、水谷慶一、松本清張)(1975年1月) ※座談会(シンポジュウム) |
| 97022(さ) | 対談■「作家にとって実生活とはなにか<対談・平野謙>」『群像』(1975年2月) ※対談 |
| 97023(購入済) 683 |
「写楽の謎の「一解決」」(1975年2月) |
| 97024(き) | 対談■『魏志』の「倭人伝」をどう読むか」<対談・直木孝次郎>(1975年4月) ※対談 |
| 97025(購入済) 606 |
「夏島」(1975年6月) |
| 97026(け)(購入済) 728 |
対談■「現代新聞論--いま何を報道すべきか<対談・桑原武夫>」(1975年8月) ※対談 |
| 97027 | 「本の岐れと末」『別冊文藝春秋(134)』(1975年12月) |
| 97028(原題)(購入済) 809 |
「古風土記」(1976年1月~1977年8月)(改題=私説古風土記) |
| 97029 | 「倭国の「漢」地帯」(1976年1月) |
| 97030(め) | 対談■「明治の小説・現代の小説<対談・木村毅>」(1976年1月) ※対談 |
| 97031(こ) | 座談会■「古代日本人のことばと文学<座談会=青木和夫、大野晋、中西進、松本清張>」(1976年1月) ※座談会 |
| 97032(し) | 「沙翁と卑弥呼」(1976年6月) ※さ‐おう〔‐ヲウ〕【沙翁】 《「沙」は「沙比阿」などの略》シェークスピアのこと。しゃおう。 |
| 97033(た) | 火?教と中国文化<対談・石田幹之助>(1976年6月) ※対談 |
| 97033(か) | 対談■火?教と中国文化<対談・石田幹之助>(1976年6月) ※対談 |
| 97034 | 箒売りの内職『太陽』(1975年7月) |
| 97035(し)(購入済) 741 |
「雑草の実〈自伝抄〉」『讀売新聞 夕刊』(1976年6月16日~7月9日)■エッセイ■ |
| 97036 | 「北一輝と児玉誉士夫」(1976年7月) |
| 97037 | 「日本の「黒い霧」史の中の主役たち」(1976年9月10日~10月8日) |
| 97038 | 「倭」と「倭人」の相違『朝日新聞・夕刊』(1970年3月12日) |
| 97039(し) | 私を語る--思考と提出『國文学18(7)』〔學燈社〕(1973年6月) |
| 97040(へ) | 対談■「ペルシャから奈良への道<対談・平山郁夫>」(1977年1月1日~1月15日) ※対談 |
| 97040(へ)(購入済) 727 |
対談■「ペルシャから奈良への道<対談・平山郁夫>」(1977年1月1日~1月15日) ※対談 |
| 97041(し) | 私の推理小説作法(自作解説)『松本清張自選傑作短篇集』〔讀賣新聞社〕(1976年6月10日) |
| 97042(わ) | 対談■私の芝居遍歴<対談・川口松太郎>『オール讀物』(1972年10月) ※対談 |
| 97043 | 「白の謀略」『別冊文藝春秋』(1977年3月) |
| 97044 | 「「多額納税者」のつぶやき」(1977年6月) |
| 97045 | 「倭人伝「其他旁国」参上」(1977年5月) |
| 97046 | 「倭人伝」一大率の新考『朝日新聞』(1975月2月13日~14日) |
| 97047(な) | 対談■「ナゾの原日本人と大和民族形成の秘密<対談・森浩一>」(1977年10月22日) ※対談 |
| 97048 | 「「万世一系」天皇制の研究」(1978年1月) |
| 97049(れ) | 対談■歴史をうがつ眼<対談・青木和夫>『国文学・解釈と鑑賞』(1978年6月) ※対談 |
| 97050 | 「社会派推理小説への道程」(1978年6月) |
| 97051(さ・や) | インタビュー■「邪馬台国」(インタビュー書評)『週刊現代』〔講談社〕(1977年3月10日) <座談会・江上波夫他> ※座談会? |
| 97052 | 「日本人よ何処へ行く」(1978年7月9日~7月16日) |
| 97053(け) | 対談■「言論の自由があってタブーのない社会を<対談・城山三郎>」(1979年1月5日) ※対談 |
| 97054(購入済) 686・686__02 |
「特派員」(1979年2月) |
| 97055 | リアリティ『現代推理小説大系九』〔講談社〕(1972年4月8日) |
| 97056 | 倭国の大乱と卑弥呼『邪馬台国の常識』〔毎日新聞社〕(1974年11月) (編者) |
| 97057 | 倭国の「漢」地帯『諸君!』(1976年1月) |
| 97058(か) | 対談■学界未公認=松本・塩道説<対談・池島信平>『文学よもやま話 上 池島信平対談集』〔文藝春秋〕(1974年2月10日) ※対談 |
| 97059(か) | 対談■カンボジア内戦で生じるアジアの嵐<対談・松本三郎>『週刊読売』(1979年1月28日) ※対談 |
| 97060(原題) | 「奇怪な斉明紀」『朝日新聞』(1979年1月28日)(改題=奇怪な「斉明記」) |
| 97061(き) | 追悼&弔詞■追悼・木々高太郎/木々先生と私(1970年10月31日) ※追悼&弔詞 |
| 97062 | 菊池寛賞受賞を喜ぶ(第26回菊池寛賞発表)『文藝春秋・56(12)』(1978年12月) |
| 97063(こ・ま) | 座談会■古代史が結ぶ日本とベトナム/「マナシカタマ」の符号<座談会=江上波夫、大林太良、松本清張> 『朝日ジャーナル』(1974年2月1・15日) ※座談会 |
| 97064(こ) | 対談■古代史の朝鮮と日本<対談・金錫享>『中央公論』(1972年12月) ※対談 |
| 97065(こ) | 対談■子供が見捨てられる時代<対談・野村芳太郎>『婦人公論』(1979年12月) ※対談 |
| 97066 | 古代イランと飛鳥『朝日新聞』(1978年12月4・5日) ※再録『清張古代史記』〔日本放送出版協会〕(1982年11月) |
| 97067 | 「五」の話『オール讀物』(1974年8月) |
| 97068(や) | シンポジュウム■「邪馬台国--流動する東アジアの中で」(シンポジュウム)共著・藤間生大・上田正昭・田辺昭三・水谷慶一 『角川選書84』(1976年4月30日) ※シンポジュウム |
| 97069-00~09(し) | シンポジュウム■古代史シンポジュム国家成立の謎(朝日新聞社主催)(1977年1月20・21日) 出席者(井上貞光、大塚初重、杉山二郎、直木孝次郎、西嶋定生、森浩一、松本清張) 〔細目〕司会者挨拶/講演補足とシンポジュムの主なテーマ/稲荷山古墳の鉄剣銘/磐井の反乱/古墳の分布・鏡 /任那と日本/仏教・蘇我氏/国家成立の時期/まとめ ※『国家成立の謎』平凡社(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 97070(さ) | 対談■財界からみたロッキード事件<対談・三鬼陽之介>特集・三木武夫頑張りの背景『中央公論91(10)』(1976年10月) ※対談 |
| 97071 | 作品解説・編『海外推理小説傑作選』全六巻 〔集英社〕(1978年5・6・7・11月) |
| 97072 | 作家にきく一時間(インタビュー書評)松本清張「地の骨」(上・下)『週刊小説』(1975年12月12日) |
| 97073(さ) | 対談■作家にとって実生活とは何か<対談・平野謙>『群像』(1975年2月) ※対談 |
| 97074 | 飛鳥保存と政府の”熱意”『朝日新聞/夕刊』(1970年6月17日) |
| 97075 | あのころのこと『新潮日本文学五十 松本清張集 月報19』〔新潮社〕(1970年3月) |
| 97076 | あとがき■あとがき『邪馬台国の常識』〔毎日新聞社〕(1974年11月) |
| 97077 | 歳月の砂(或る「小倉日記」伝妙)『現代文章宝館』〔柏書房〕(1979年11月21日) |
| 97078 | 伊勢参宮へのいざない『日本人のための日本再発見・樋口清之編』〔朝日出版〕(1973年10月10日) |
| 97079 | イラン高原の「火」の旅から『太陽』(1973年9月 |
| 97080 | カイエ・ダール<図説>火の路--ペルセポリスから飛鳥へ『芸術新潮30(Ⅰ)』(1979年1月) |
| 97081 | 解説■解説・『江戸川乱歩全集一二』〔講談社〕(1970年3月) ※解説 |
| 97082(か) | 追悼&弔詞■追悼・平野謙/活字と肉声(1978年6月) ※追悼&弔詞 |
| 97083(は) | ガラスの壁と伊都国『朝日新聞』(1976年2月5日) 改題・瑠璃の壁と伊都国 再録『清張古代史記』〔日本放送出版協会〕(1982年11月)読み(玻璃=はり/ガラスの異称) |
| 97084 | 監修■監修・『木々高太郎全集(全六巻)』〔朝日新聞社〕(1970年10月~1971年3月) ※監修 |
| 97085 | 監修■監修・『新青年傑作選(全五巻)〔立風書房〕(1970年?月) ※監修 |
| 97086(き) | 座談会■疑獄の系譜--その構造と風土--<座談会=金原左門、川村善二郎、原田勝正、門馬晋・司会/松本清張> 『疑獄100年史』『読売新聞』(1977年3月20日) ※座談会 |
| 97087(き) | 対談■魏志倭人伝をめぐる国際環境<対談・西嶋定生>『古代探求』『朝日新聞』(1977年4月20日) 「古代探求」『文藝春秋』とは別書 ※対談 |
| 97088(ま) | 対談■松本清張の天皇史発掘_連載対談<対談・直木孝次郎>『サンデー毎日』(1975年1月5日~19日) ※対談 |
| 97089(け) | 対談■激動するアジアを見つめて<対談・ウイルフレッド・G・バーチェット>『文藝春秋49(9)』(1971年7月) ※対談 |
| 97090(け) | 座談会■下駄でつながるムオン族<座談会=・江上波夫、大林太良、松本清張>古代から結ぶ日本とベトナム(下)『朝日ジャーナル16(6)』 (1974年2月15日) ※座談会 |
| 97091(原題)(購入済) 805 |
西海道談綺の舞台をゆく『週刊文春』(1976年5月13日) (改題=「西海道談綺」紀行)〔再録=『松本清張全集52』〕(1983年11月) |
| 97092 | 寒い家からの文学『朝日新聞別集PR版』(1970年2月4日) |
| 97093 | 事件の推移をみながら(鼎談)特集・ロッキード事件国際疑惑『中央公論91(4)』(1976年4月) |
| 97094(購入済) 712 |
時刻表--ひとり旅への憧れ(値段の明治・大正・昭和風俗史)『週刊朝日』(1979年11月16日) |
| 97095(や) | 対談■邪馬台国を語る『邪馬台国の謎を探る--歴史と文学の旅』<対談・江上波夫>〔平凡社〕(1972年10月) ※対談 |
| 97096 | 序『推理小説年鑑 一九七〇年版推理小説代表作選集』〔日本推理作家協会〕(1970年4月) |
| 97097 | 序『推理小説年鑑 一九七一年版推理小説代表作選集』〔日本推理作家協会〕(1971年4月20日) |
| 97098 | 小説『火の路』創作ノート『日本史謎と鍵』〔平凡社〕(1976年11月25日) |
| 97099 | 聖徳太子『人物日本の歴史一 飛鳥の悲歌』〔小学館〕(1974年11月25日) |
| 97100 | 聖徳太子の謎『太陽』(1972年10月) |
| 97101-01(ふ・し)(購入済) 661 |
対談■対談 昭和史発掘 不安な序章<対談・城山三郎>『文藝春秋』(1975年1月) ※対談 〔細目〕不安な序章<城山三郎>/吹き荒れるファシズム<五味川純平>/マッカーサ-から田中角栄まで<鶴見俊輔> |
| 97101-02(ふ・し)(購入済) 662 |
対談■対談 昭和史発掘 吹き荒れるファシズム<対談・五味川純平>『文藝春秋』(1975年1月) ※対談 〔細目〕不安な序章<城山三郎>/吹き荒れるファシズム<五味川純平>/マッカーサ-から田中角栄まで<鶴見俊輔> |
| 97101-03(ま・し)(購入済) 663 |
対談■対談 昭和史発掘 マッカーサ-から田中角栄まで<対談・鶴見俊輔>『文藝春秋』(1975年1月) ※対談 〔細目〕不安な序章<城山三郎>/吹き荒れるファシズム<五味川純平>/マッカーサ-から田中角栄まで<鶴見俊輔> |
| 97102(に・さ) | 神話と歴史について(第八回)『日本のなかの朝鮮文化(8)』<座談会=司馬僚太郎、井上秀雄、上田正昭、金達寿、松本清張>(1970年12月) ※座談会 〔再録〕『日本の朝鮮文化』〔中央公論社〕(1972年11月) |
| 97103(せ) | 対談■清張作品とその時代背景<対談・巌谷大四>『新刊ニュース』(1971年4月) ※対談 |
| 97104(せ) | 対談■石油危機と日本の進路<対談・朝海浩一郎>『サンデー毎日』」(1974年1月6日) ※対談 |
| 97105 | 選考経過報告(江戸川乱歩賞選考委員)『殺意の演奏』大谷半太郎著 〔講談社〕(1970年8月) |
| 97106 | 選考経過報告(江戸川乱歩賞選考委員)『仮面法廷』和久俊三著 〔講談社〕(1971年8月) |
| 97107 | 装飾古墳にみる「倭人伝」『藝術新潮25(11)』(1974年11月) |
| 97108(そ) | 対談■続日本文学をさかのぼる<対談・増田勝実>『國文學18(6)』〔學燈社〕(1973年6月) ※対談 |
| 97109 | 高井戸巡査殺し『週刊新潮』(1974年1月3日) |
| 97110 | 高松塚古墳を推理する『朝日新聞・夕刊』(1972年4月19日) |
| 97111 | 高松塚の製作年代再論『朝日新聞・夕刊』(1973年6月29日) |
| 97112 | 高松塚壁画の年代推説『世界』(1972年6月) |
| 97113 | 中国侵略の後始末をきちんとつけよ<対談・新井宝雄>『サンデー毎日』(1971年8月1日) |
| 97114(ち) | 追悼&弔詞■追悼・角川源義/弔詞(1975年12月15日) ※追悼&弔詞 読み=角川源義(カドカワゲンヨシ) |
| 97115(ち) | 追悼&弔詞■弔詞『俳句25(2)』(角川源義追悼特集)(1976年2月) ※追悼&弔詞 読み=角川源義(カドカワゲンヨシ) |
| 97116(ふ) | 頂上の犠牲山羊 文士が見た田中角栄(緊急特集・田中逮捕以後の日本)『中央公論91(9)』(1976年9月) |
| 97117 | 追悼&弔詞■追悼の辞『和田芳恵先生を偲ぶ』長万部町(北海道)和田芳恵先生を讃える会(1978年6月10日) ※追悼&弔辞 |
| 97118(い) | 鉄剣銘解釈への疑問(稲荷山古墳の謎)『芸術新潮29(11)』(1978年11月) |
| 97119(た) | 天皇陵を推理する<対談・江上波夫>『藝術新潮24(1)』(1973年1月) ※対談 |
| 97119(て) | 対談■天皇陵を推理する<対談・江上波夫>『藝術新潮24(1)』(1973年1月) ※対談 |
| 97120(さ) | 銅鼓--銅鐸のナゾを解くカギ<座談会=江上波夫・大林太良・松本清張>古代史から結ぶ日本とベトナム(中)『朝日ジャーナル16(5)』 (1974年2月4日) ※座談会 |
| 97121 | 銅鼓とガンダーラ仏--私のコレクション(秘蔵二十五)『藝術新潮26(7)』(1975年7月) |
| 97122 | 東西日本文化はなぜ断たれたか『文藝春秋50(2)』(1972年2月) |
| 97123(せ) | 東方の恐怖と歓喜『世界の名画三 アングルとドラクロワ 新古典派とロマン派』井上靖、高階秀爾〔中央公論社〕(1972年4月10日) |
| 97124(な) | 解説■奈良朝廷で活躍したペルシャ人僧(解説)『中央公論54(6)』(1976年6月) ※解説 |
| 97125(さ・ふ) | 日本官僚政治の病根--ファシズムを生む密室構造<座談会=太田薫、岡義達、松本清張> 『エコノミスト50(27)』(1972年6月27日) ※座談会 |
| 97126 | 日本史への架け橋『東京新聞』」(1974年10月14日~17日) |
| 97127(に) | 対談■日本の神話世界をめぐって<対談・上田正昭> 『続古代史の謎』〔青木書店〕対談=1975年4月15日(1976年12月1日) ※対談 |
| 97128 | 歴史家『文学よもやま話上』『文藝春秋』1974年2月10日) |
| 97129(さ) | 日本の朝鮮文化<座談会=司馬遼太郎、井上秀夫、上田正昭、金寿達、松本清張>第8回神話と歴史について 『日本の中の朝鮮文化』(1970年12月) ※座談会 |
| 97130 | 日本の文化(エコノミスト創刊50周年記念講演)『エコノミスト50(28)』(1972年4月) |
| 97131(に) | 対談■日本文学をさかのぼる<対談・増田勝実>特集・日本文学の始原『國文学18(3)』學燈社(1973年3月) ※対談 |
| 97132(原題) | 日本民俗の系譜『太陽』(1978年7月)(改題=日本人の源流を探る) |
| 97133(に) | 対談■日本を沈没させる元凶は東大だ<対談・宇井純>宇井純のシリーズ告発『週刊サンケイ』(1974年2月15日) ※対談 |
| 97134(に) | 東アジアの中の日本古代--倭の女王卑弥呼『日本史の中の女性--卑弥呼から唐人の吉まで』『毎日新聞』(1978年9月30日) |
| 97135(ま) | 文藝春秋と私 埋没された青春『文藝春秋』(1979年6月) |
| 97136(つ) | 編集委員『角田喜久夫全集』(全十三巻)〔講談社〕(1970年8月~1971年8月) |
| 97137(や) | 編者のことば『邪馬台国99の謎--どこに在り、なぜ消えたのか』『サンポーブックス90』〔産報〕(1975年9月) |
| 97138 | まえがき『最新ミステリー選集二 家紋』〔光文社〕(1971年8月) |
| 97139 | まえがき『最新ミステリー選集三 新開地の事件』〔光文社〕(1971年9月) |
| 97140(さ) | 松本清張対司馬遼太郎(座談会)『噂』(1971年11月) |
| 97141 | 苗族の餅『朝日新聞・夕刊』(1970年1月21日) 読み(苗族=ミャオゾク) |
| 97142 | モスクワの惨事と「もく星」号の間『週刊朝日』(1972年12月15日) |
| 97143(し) | ヤポネシア古代学の未来(シンポジュウム)『市民講座・日本古代文学入門一』共編者江上波夫 『読売新聞社』(1976年5月20日) <出席者=森浩一・谷川健一・大林太良・井上秀雄・上田正昭・国分直一・中西進・山田秀三・李進熈・司会/鈴木武樹> ※シンポジュウム |
▲ページのTOP▲ ●95000●96000●97000●98000●99000●不明 ▼ページの最後▼
| コードNo 98000 |
 |
| 98001 | 「古事記と日本書紀の関係」(1980年5月) |
| 98002 | 「「魏志倭人伝」の盲点」(1980年8月) |
| 98003 | 「「古事記」新解釈ノート」(1980年10月) |
| 98004(購入済) 614 |
「不運な名前」(1981年2月) |
| 98005 | 「道鏡事件と宇佐八幡」(1981年4月) |
| 98006 | 「白い影」『ミセス』(1981年1月~1984年3月休載) |
| 98007(購入済) 609 |
「断崖」(1982年5月) |
| 98008(て) | 対談■「天才たちの虚実」<対談・針生一郎>『波』(1982年6月) ※対談 |
| 98009(や) | 「吉野ヶ里遺跡」探訪記「邪馬台国」は見えたか『FOCUS』(1989年5月12日) |
| 98010 | 「稲荷山鉄剣をめぐる一仮説」(1982年10月12日~13日) |
| 98011(購入済) 全集:月報 |
「着想ばなし」(1982年11月~1984年4月) |
| 98012(ま) | 座談会■「松本清張説」をめぐる共同討議 古代を検証する<座談会・青木和夫、中西進、森浩一> (1983年9月) ※座談会 |
| 98013(購入済) シリーズ28 |
「松本清張短篇小説館」(全5話)(1983年9月~1985年12月) 1話「思託と元開」(704) 2話「南半球の倒三角」(565-07) ●【名札のない荷物】の2話 3話「信号」(607) 4話「老十九年の推歩」(608) 5話「二醫官傳(両像・森鴎外)」(685)(改題・加筆/両像・森鴎外) |
| 98014(し)(購入済) 704 |
「松本清張短篇小説館 思託と元開」(全5話 1/5)(1983年9月~10月) ● 「松本清張短篇小説館」(全5話)(1983年9月~1985年12月) |
| 98015(し)(購入済) 607 |
「松本清張短篇小説館 信号」(全5話 3/5)(1984年2月・4月・6月) ● 「松本清張短篇小説館」(全5話)(1983年9月~1985年12月) |
| 98016(し)(購入済) 664 |
対談■「小説ほど面白いものはない」<対談・山崎豊子> (1984年3月) ※対談 |
| 98017 | 「邪馬台国=紀行」〔旺文社〕(1981年1月) |
| 98018 | 「「霧プロ」始末記--そもそもは「黒地の絵」の映画化から生まれた話だった」(1984年10月26日) ■エッセイ■ |
| 98019(ろ)(購入済) 608 |
「松本清張短篇小説館 老十九年の推歩」(全5話 4/5)(1984年10月11・1985年1月) ● 「松本清張短篇小説館」(全5話)(1983年9月~1985年12月) |
| 98020 | 「中世への招待」(1985年1月) |
| 98021 | 「読書備忘カード」(1984年1月) |
| 98022-00 | 「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) 長岡京廃都の謎『古史眼烟』(98022-01) 銅剣は「祭器」か『古史眼烟』(98022-02) 旧約聖書と日本古典『古史眼烟』(98022-03) 書紀・倭人伝の「資料」考証『古史眼烟』(98022-04) 九州雑筆『古史眼烟』(98022-05) 稲荷山・船山両鉄剣の製作地『古史眼烟』(98022-06) 「呪術」の合唱『古史眼烟』(98022-07) |
| 98022-01(こ) | 長岡京廃都の謎『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-02(こ) | 銅剣は「祭器」か『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-03(こ) | 旧約聖書と日本古典『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-04(こ) | 書紀・倭人伝の「資料」考証『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-05(こ) | 九州雑筆『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-06(こ) | 稲荷山・船山両鉄剣の製作地『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98022-07(こ) | 「呪術」の合唱『古史眼烟』『図書』(1985年1月~7月・9月) ●「古史眼烟」『図書』(1985年1月~7月・9) |
| 98023 | 「「石川達三」メモ」(1985年4月) |
| 98024(り) | 追悼&弔詞■追悼・石川達三/リアリズムの多彩(1985年4月) ※追悼&弔詞 |
| 98025(購入済) 685(に・も・り) (原題) |
「二醫官傳(両像・森鴎外)」(全5話 5/5)(1985年5月~10月・12月)(改題・加筆/両像・森鴎外) ● 「松本清張短篇小説館」(全5話)(1983年9月~1985年12月) |
| 98026 | 「「霧の会議」取材の旅」(1984年11月19日~21日)■エッセイ■ |
| 98027 | 「新春放談「話の雑炊」」(1986年2月) |
| 98028 | 筆のはじめに(天保図録・上)『日本歴史文学館二四』〔講談社〕(1987年4月20日) |
| 98029 | 「「霧の会議」を終えて」(1986年9月22日) |
| 98030(購入済) 655 |
「紙碑」(1987年5月) |
| 98031(購入済) 702 |
「国際推理作家会議で考えたこと」(1988年1月) |
| 98032(く)(購入済) 599 |
「骨折(グルノーブルの吹奏)」『小説現代』(1988年1月) |
| 98033 | 「菊池寛の文学」(1988年2月) |
| 98034 | 「眼」『文藝春秋』(1988年5月) |
| 98035 | 「私観・昭和史論」(1988年6月) |
| 98036 | 「神格天皇の孤独」(1989年3月) |
| 98037(て)(購入済) 677 |
「泥炭地」』(1989年3月) |
| 98038 | 船山・稲荷山刀は百済製の疑い一仮説『文藝春秋』(1983年3月) |
| 98039 | 「52歳にして「歴史」を作った江副浩正の「砂の器」」(1989年4月25日) |
| 98040(購入済) 687 |
「吉野ケ里と邪馬台国の影」(1989年5月) |
| 98041 | 「まだまだ早い「吉野ケ里は邪馬台国」説」(1989年5月19日) |
| 98042(購入済) 688 |
「逃げ水 邪馬台国」(1989年7月) |
| 98043(購入済) 684 |
密教の水源をみる 空海・中国・インド〔講談社〕(1984年4月17日) ※講談社文庫、1994年6月=購入可 |
| 98044(し) | 文庫版のためのあとがき『白と黒の革命』〔文春文庫/文藝春秋〕(1981年12月25日) |
| 98045(れ) | 松本清張の邪馬台国論--霊力を失った卑弥呼は人民に殺されたか?『AERA』(1989年6月13日) |
| 98046(こ) | 対談■好奇心旺盛な文壇の巨匠は年中無休<対談・イーデス・ハンソン>『週刊文春24(3)』(1982年1月21日) ※対談 |
| 98047-00(こ・と) | シンポジュウム■古代出雲・荒神谷の謎に挑む『古代出雲・荒神谷の謎に挑む』/討論〔角川書店〕(1987年5月15日) シンポジュウム山陰中央新報社主催 ※シンポジュウム(参加者不明) |
| 98047-01(こ・そ) | シンポジュウム■荒神谷の様々な問題『古代出雲・荒神谷の謎に挑む』/総論〔角川書店〕(1987年5月15日) シンポジュウム山陰中央新報社主催 ※シンポジュウム(参加者不明) |
| 98048 | 安心院『文藝春秋』(1981年8月) ※読み(安心院=アジム) |
| 98049 | あとがき■あとがき 『正倉院への道』〔日本放送出版協会〕(1981年11月1日) |
| 98050(き) | アンケート■アンケート・消える国道(アンケート回答とエッセイ)特集・残したい”日本” 『藝術新潮・38(6)』(1987年6月1日) ※アンケート |
| 98051(い) | あとがき■あとがき『天保図録 下 日本歴史文学館二五』 『筆のはじめに(下)筆者インタビュー』〔講談社〕(1987年5月20日) ※インタビュー |
| 98052 | あとがき■あとがき『古代出雲・荒神谷の謎に挑む』〔角川書店〕(1987年5月15日) |
| 98053 | 荒野と屋台と『旅』(1989年9月) |
| 98054 | 出雲の荒神谷遺跡から『銅剣・銅鐸・銅矛と出雲王国の時代』〔日本放送出版協会〕(1986年9月20日) |
| 98055-00(こ) | シンポジュウム■『国家成立の謎』〔平凡社)(1980年4月5日) 出席者(井上貞光、大塚初重、杉山二郎、直木孝次郎、西嶋定生、森浩一、松本清張) 〔細目〕司会者挨拶/講演補足とシンポジュムの主なテーマ/稲荷山古墳の鉄剣銘/磐井の反乱/古墳の分布・鏡 /任那と日本/仏教・蘇我氏/国家成立の時期/まとめ ※古代史シンポジュム国家成立の謎(朝日新聞社主催)(1977年1月20・21日) ※シンポジュウム |
| 98055-01(こ) | シンポジュウム■司会者挨拶『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-02(こ) | シンポジュウム■講演補足とシンポジュムの主なテーマ『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-03(い・こ) | シンポジュウム■稲荷山古墳の鉄剣銘『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-04(い・こ) | シンポジュウム■磐井の反乱『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-05(こ) | シンポジュウム■古墳の分布・鏡『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-06(こ・み) | シンポジュウム■任那と日本『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-07(こ・ふ) | シンポジュウム■仏教・蘇我氏『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-08(こ) | シンポジュウム■国家成立の時期『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98055-09(こ・ま) | シンポジュウム■まとめ『国家成立の謎』〔平凡社〕(1980年4月5日) ※シンポジュウム |
| 98056(の) | 追悼&弔詞■野間さんとわたし『追悼・野間省一』追悼集刊行委員会〔講談社〕(1985年8月10日) ※追悼&弔詞 |
| 98057(か) | 江戸川乱歩『神とともに行け--弔辞大全Ⅱ・開高健編』〔新潮文庫/新潮社〕(1986年12月30日) |
| 98058 | 私が天皇の死を聞いた瞬間『週刊文春』(各界35氏が語る)(1989年1月19日) |
| 98059(き) | 追悼&弔詞■木村毅氏と私(特集・木村毅先生追悼)『早稲田大学史記要・ (13)』(1980年5月) ※追悼&弔詞 |
| 98060(あ) | 芸術の対立 批判に偏見があってはならぬ/「青木繁と坂本繁二郎」批判への批判『朝日新聞・夕刊/学芸欄』(1982年10月4日) |
| 98061 | 古代西アジア雑記『新潮古代美術館二 栄光の大ペルシャ帝国』〔新潮社〕(1981年5月) 改題=古代西アジアと「火の路」と |
| 98062(購入済) 682 |
執念『海』(1983年1月) |
| 98063 | 護摩とゾロアスター教(1983年) |
| 98064(改題)(購入済) 805 |
「西海道談綺」紀行 〔再録=『松本清張全集52』〕(1983年11月)(原題=西海道談綺の舞台をゆく)(97091) (1976年5月13日) |
| 98065 | 祭神と謎の神事『旅・新年号』(1983年1月) |
| 98066 | 雑読愚注『小説新潮スペシャル』(1981年1月) |
| 98067(購入済) 731 |
文学に現れた横須賀(横須賀市教育委員会編)(1982年3月31日) |
| 98068 | 周辺の随想『クラクラ日記』坂口三千代著 〔筑摩文庫〕(1989年10月) |
| 98069 | 取材の世界『オール讀物』(1989年3月) |
| 98070=900? | 受賞者のことば『芥川賞全集五』 『文藝春秋』(1983年6月25日) 「感想・(芥川賞受賞)『松本清張の世界 文藝春秋10月臨時増刊号』」(900) |
| 98071 | 女王国の範囲『銅鐸と女王国の時代』〔日本放送出版協会〕(1983年10月1日) |
| 98072(あ・し) | 座談会■『正倉院への道』〔日本放送出版協会〕(1981年11月1日)座談会、あとがき ※座談会&あとがき |
| 98073 | 賞と運『芥川賞小事典--芥川賞全集別巻』小田切進編 『文藝春秋』(1983年7月1日) |
| 98074 | 書紀の「巫」(?)『國學院雑誌87(4)』(1986年4月) |
| 98075 | スイス日記妙「聖獣配列」連載の前に『週刊新潮』(1983年8月25日) |
| 98076 | 「漏刻」遺跡か『文藝春秋』(1983年1月) |
| 98077 | 着実な歩みをつづけて『夏目漱石展』〔日本近代文学館〕(1987年5月28日) |
| 98078(ち) | インタビュー■著者インタビュー(天保図録)『日本歴史近代文学館二五』(1987年5月20日) ※インタビュー |
| 98079(て) | 対談■天皇はどこから来たか「藤ノ木古墳」と「騎馬民族説」を結ぶ点と線<対談・江上波夫> 『朝日ジャーナル」』1989年1月6日) ※対談 |
| 98080-00(購入済) 666 |
銅鐸と女王の時代〔日本放送出版協会〕(1983年10月1日) 〔細目〕 まえがき(98080-01) 女王国の範囲(98080-02) 銅鐸と邪馬台国の時代(98080-03)※シンポジュウム(共同討論) |
| 98080-01(ま)(購入済) 667 |
『銅鐸と女王の時代』/まえがき 〔日本放送出版協会〕(1983年10月1日) 〔細目〕 まえがき(98080-01) 女王国の範囲(98080-02) 銅鐸と邪馬台国の時代(98080-03)※シンポジュウム(共同討論) |
| 98080-02(し)(購入済) 668 |
『銅鐸と女王の時代』/女王国の範囲 〔日本放送出版協会〕(1983年10月1日) 〔細目〕 まえがき(98080-01) 女王国の範囲(98080-02) 銅鐸と邪馬台国の時代(98080-03)※シンポジュウム(共同討論) |
| 98080-03(し)(購入済) 669 |
『銅鐸と女王の時代』/銅鐸と邪馬台国の時代<共同討論=岡崎敬・門脇禎二・佐原真・水野正好・高島忠平・高倉洋彰・司会/松本清張> ※シンポジュウム(共同討論) 〔日本放送出版協会〕(1983年10月1日) 〔細目〕 まえがき(98080-01) 女王国の範囲(98080-02) 銅鐸と邪馬台国の時代 (98080-03) ※シンポジュウム(共同討論) |
| 98081 | 年頭・作家は何を考えたか、1976年元旦『鳩よ!』(1989年1月) |
| 98082 | なぜ「霧プロ」を作ったか(特集・わるいやつら)『キネマ旬報(789)』(1980年7月1日) |
| 98083(は) | インタビュー■初めての自作の脚本を執筆して(インタビュー・品田雄吉) 『キネマ旬報/特集・疑惑(884)』(1982年9月15日) ※インタビュー |
| 98084 | 走水の暗い画『日本経済新聞社・文化欄』(1981年4月5日) |
| 98085 | 『清張古代史記』〔日本放送出版協会〕(1982年11月) 玻璃の壁と伊都国(改題) 原題=ガラスの壁と伊都国『朝日新聞』(1976年2月5日)の再録 読み(玻璃=はり/ガラスの異称) |
▲ページのTOP▲ ●95000●96000●97000●98000●99000●不明 ▼ページの最後▼
| コードNo 99000 |
 |
| 99001(あ) | 私が推す「新国宝」(アンケート)『藝術新潮』(1990年1月) |
| 99002 | 「血の洗濯」『文藝春秋』(1990年9月) |
| 99003 | 「湾岸後のソ連-私はこう分析する」(1991年3月7日) |
| 99004(て) | 対談■「天皇になろうとした男 足利義満」<対談・今谷明>(1991年3月15日) ※対談 |
| 99005 | 「ソ連政変の謎に迫る」(1991年9月5日) |
| 99006 | 「直弧文の一解釈」『文藝春秋』(1991年11月) |
| 99007(こ)(購入済) 665 |
「江戸綺談 甲州霊獄党」(1992年1月2日~5月15日) |
| 99008(こ)(購入済) 699 |
座談会■「「古代史のナゾ」を解:大化の改新は本当にあったのかく<座談会・門脇禎二、佐原眞、松本清張>」 (1992年1月) ※座談会 |
| 99009(せ) | インタビュー■「「世界が激動しても人間は変わらないんだよ」作家生活40周年記念インタビュー」(1992年4月7日) ※インタビュー |
| 99010(購入済) 618 |
「一九五二年日航機「撃墜」事件」(1992年4月30日) |
| 99011(わ・ま) | 対談■わが映画・ドラマ・文学「松本文学はドフトエフスキー+ポー」<対談・新井満>『週刊文春』(1991年10月3日) ※対談 |
| 99012 | 一服の烟『神々の乱心』の奥にある後宮の魔性『週刊文春』(1991年8月8日) |
| 99013 | 激震 永田町 次の総理私はこの人を推す『週刊文春』(1991年10月17日) |
| 99014(さ)(購入済) 071 |
「削除の復元」『松本清張全集「66」(1996/08/03)』〔文藝春秋〕(1990年1月) |
| 99015(さ・に) | 世界に答える日本文化の特質・日本文化をこう考える 鎖国がなかったら「印象派」は生まれなかった・・・『藝術新潮42(8)』(1991年8月) |
| 99016 | 日本書紀を読む『日本書紀を読む 岩波ブックレット200』岩波書店(1991年6月13日) |
| 99017(お) | 振替休日なんて要らん(オピニオンワイド天下の”暴論”13)『週刊文春』(1992年1月16日) |
▲ページのTOP▲ ●95000●96000●97000●98000●99000●不明 ▼ページの最後▼
| コードNo 90000 |
 |
| 90000 | 人生には卒業学校名の記入欄はない『青春手帳』 ※発表年代不明 |
| 90001 | わたしの北一輝観『民藝の仲間(139)』〔劇団民藝〕 再録「松本清張研究1」(砂書房、1996年9月) ※発表年代不明 |
| 90002 | 俳句「朝日俳句会」(1943年)『ビジネスマン読本 松本清張』〔日本能率マネージメントセンター〕(1993年3月1日) ※発表年代不明 |