| 0C | 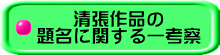
【疑/疑問の「疑」】 |
0C |
| 0C | 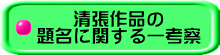
【疑/疑問の「疑」】 |
0C |
清張作品の題名は「黒の...」とか「霧の旗」・「波の塔」など「の」が多く使われている。
ぼんやり題名の特徴などを考えていたと、きその特徴を整理してみようと思い立った。
まさに蛇足的考察である!
(第二部)
| No0C | 08/10/19 | ●疑/疑問の「疑」 「疑」です。疑惑の「疑」・疑問の「疑」 |
| 「疑惑」/「サンデー毎日・臨時増刊」(1956年(昭和31年)7月号)(原題=昇る足音) 「群疑」/「キング」(1957年(昭和32年)10月号) 「死の枝 第四話 史疑」/「小説新潮」(1967年(昭和42年)5月号) 「疑惑」/「オール讀物」(1982年(昭和57年)2月号) 小説では以上である。 「疑惑」は同姓同名だ。「疑惑」(オール讀物)は時代小説 同姓同名で一方が時代小説のパターンで「突風」。両方時代小説のパターン「転変」「逃亡」 題名が2文字なのは、前に「風」を取り上げたのと同じ理由だからなのだろう。 ただ「風」は「フウ」と読むことで2文字になる事が多いのだが、「疑」は「ギ」である。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 疑 (ぎ)は、仏教が教える煩悩のひとつ。 「疑」とは、仏教の示す真理に対して思い定むることなく、まず疑ってかかる心である。このような心をもつ限り 、いかなる教えも自心は受け付けることはない。 疑は、六大煩悩の一つである。 「死の枝 第四話 史疑」は古代史を連想させる題である。 新井白石の著作「史疑」とあるので調べたら、 http://www015.upp.so-net.ne.jp/gofukakusa/daijiten-arai-hakuseki.htm より >古代史については、神話に合理的解釈を試み、その中に含まれる歴史的事実を究明しようとした >『古史通』があり、さらに『史疑』を著わし、六国史の文献批判を行なったが、これは現在ほとんど >伝わっていない。 古代史など、その他では 「日本の黒い霧 第三話 二大疑獄事件 -昭電・造船汚職の真相-」(「文藝春秋」(1960年)) 「古代史疑」(「中央公論」(1966年)) 「遊古疑考」(「芸術新潮」(1971年)) 「松本清張社会評論集 Ⅰ 「示談」への疑惑」 「疑通史-古代信仰は日本固有のものか」 である。 2008年10月19日記 |