| その 十九 |
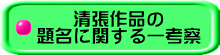
【風】 |
その 十九 |
清張作品の題名は「黒の...」とか「霧の旗」・「波の塔」など「の」が多く使われている。
ぼんやり題名の特徴などを考えていたと、きその特徴を整理してみようと思い立った。
まさに蛇足的考察である!
(第三部:その十九).
| その十九 22/10/21 |
●風 「数の風景」【歌のない歌集】:第一話 「黄色い風土」(原題:黒い風土) 「骨壺の風景」【無宿人別帳】:第二話 「突風」【影の車】:第八話 「梅雨と西洋風呂」【黒の図説】:第六話 「風の視線」 「風紋」(原題:流れの結像) 「突風」【紅刷り江戸噂】:第三話 「風の息」(上)(下) 「信玄軍記/炎風」 「風炎」《改題=「殺人行おくのほそ道(上)」・「殺人行おくのほそ道(下)」》 「風圧」《改題=「雑草群落(上)」・「雑草群落(下)」》 ※エッセイで 【暗色調(ダークトーン)の中の風景】(エッセイ:2020年7月16日購入)もあった。 |
「風」にもいろいろある。 【風景】【風土】【突風】【風呂】【風紋】【炎風】 【風呂】だけが異質だ。なぜ、風に「呂」と書いて風呂なのだろう? ちなみに【呂】は ろ【呂】 読み方:ろ [常用漢字] [音]ロ(呉) リョ(漢) [一]〈リョ〉雅楽などで、陰の調子。「大呂・南呂・律呂」 [二]〈ロ〉当て字。「語呂・風呂(ふろ)」 [難読]呂宋(ルソン)・呂律(ろれつ) 年代順に並べてみた。各年代に満遍なく書かれている。 「突風」と「風景」がそれぞれ二作品。短編長編が、半々ぐらい。「風の○○」も二作品。 とにかく満遍なく登場している。 「信玄軍記/炎風」 【信玄軍記(河出新書)】 1956年(昭和31年)3月●短編/時代 「黄色い風土」(原題:黒い風土) 【北海道新聞】 1959年(昭和34年)5月22日〜1960年(昭和35年)8月7日●長編 「風の視線」【女性自身】 1961年(昭和36年)1月3日号〜12月18日号●長編 「突風」【影の車】:第八話 【婦人公論】 1961年(昭和36年)8月号●短編 「風紋」(原題:流れの結像) 【現代】 1967年(昭和42年)1月号〜1968年(昭和43年)6月号●長編 「突風」【紅刷り江戸噂】:第三話 【小説現代】 1967年(昭和42年)6月号〜8月号●短編/時代 「梅雨と西洋風呂」【黒の図説】:第六話 【週刊朝日】 1971年(昭和46年)7月17日号〜12月11日号●長編 「風の息」(上)(下) 【赤旗】 1972年(昭和47年)2月15日号〜1973年(昭和48年)4月14日号●長編 「骨壺の風景」【新潮】 1980年(昭和55年)1月号●短編 「数の風景」【歌のない歌集】:第一話 【週刊朝日】 1986年(昭和61年)3月7日号〜1987年(昭和62年)3月27日号●長編 少々ネタ切れの感がある。『風景』として取り上げていた。 今回を持って【題名に関する一考察】は完結とします。 完結にするに当たって三部構成にしていましたが、一つにまとめます。 2022年10月21日記 |