| その 十六 |
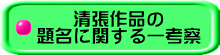
【草】 |
その 十六 |
清張作品の題名は「黒の...」とか「霧の旗」・「波の塔」など「の」が多く使われている。
ぼんやり題名の特徴などを考えていたと、きその特徴を整理してみようと思い立った。
まさに蛇足的考察である!
(第三部).
| その十六 | 21/11/21 | ●草 中編:【草】【黒い画集 第九話】 【週刊朝日】(1960年(昭和35年)4月号10日〜6月19日) 長編:【草笛】【新潮】(1960年(昭和35年)9月)) 短編:【百済の草】【絢爛たる流離 第三話】 【婦人公論】(1963年(昭和38年)3月号) 長編:【草の印刻】【読売新聞】(1964年(昭和39年)5月号16日〜1965年(昭和40年)5月23日号) 長編:【雑草群落】(上)(下) 【東京新聞】(1965年(昭和40年)6月号18日号〜1966年(昭和41年)11月7日号) 短編:【壁の青草】 【別冊文藝春秋73】(1966年(昭和41年)5月号) 短編:【葡萄唐草文様の刺繍】(原題=葡萄草文様の刺繍) 【オール讀物】(1971年(昭和46年)1月号) シリーズ作品で『草の径』 ※面白いのは、年代が新しくなるにつれて、タイトルが長くなっている。おもしろくもないか? |
| 作品は、短編、中編、長編と全て揃っている。 現代物ばかりで、時代物は無い。 1960年代に書かれた者が殆どだ。(「葡萄唐草文様の刺繍」は、1971年の作品) 「草」に特別な意味があるようには思えないが、「百済の草」だけは紹介作品でも取り上げているので 内容的には把握している。他の作品には特別な印象が無い。(一応全て完読している。10年以上昔) 「百済の草」の「草」に関係する部分は...紹介作品でも取り上げたが >寺の境内の草を掴んで殺されていたという。(これが、タイトルの「百済の草」の意味か?) >立っているところを刺され、仆れるときに草を掴んだとされていることに疑問を持つ。, 直接的に草が登場する。 他の作品には、題名に「草」を思わせる内容は無い。 ●雑草群落 【カバー】古美術商「草美堂」の主人・高尾庄平は30も年下の料理屋の女中・和子と一年前から関係がある。火事で焼け出された和子を新築のアパートに移らせ、デパートで家具などを買いそろえた。その買い物の途中、同業の駒井竜古堂が国立総合美術館の佐川課長と連れだってきているのに出会った。文化財保護委員の佐川は、庄平たちの業者仲間では幅をきかせている男である。−−−古美術蒐集のため金に糸目をつけぬ明和製薬の村上社長へ接近を図る庄平は竜古堂の動きに危険な策謀を感じた・・・・・・。古美術界の実態を鋭く描破した巨匠の異色の大作。 ●草の印刻 【帯】張りめぐらされた犯罪の見えない糸に戦いを挑む長篇推理小説 ●葡萄唐草文様の刺繍 (キーワード)ブリュッセル・ホテル・テーブルクロス・バーのマダム・週刊誌・刺繍・みぬま 2021年11月21日記 |