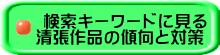
|
清張作品の書き出し300文字前後からあぶり出すキーワード!
(登録キーワードも検索する)
▼ページの最後▼
| ●映画 映画は、漠然とした記憶だが、小説にかなり登場していると思う。 犯人がアリバイを証明する為に観た映画の内容を供述する場面など記憶にある。「証言」(あるサラリーマンの証言)など印象に残っている。 ただ、今回調べてみたら、小説では映画の題名を「××」と書いていて具体的には示していない。 私の記憶は、小林桂樹主演の映画で、「西部の嵐」・「パンと恋と夢」と具体的だ。 他に、「砂の器」と「顔」を思い出す。 「砂の器」は、殺され三木謙一の足取りを調べる今西栄太郎が伊勢の映画館で調べる場面がある。 映画館の支配人である渥美清が話す場面で、映画の題名が出てくる。 「利根の朝霧」・「男の町」翌日「北海の嵐」・「大江戸の鬼」である。 小説では、「利根の風雲」・「男の爆発」・予告編「世紀の道」となっている。微妙に原作と違うところが面白い。 「顔」では映画そのものは問題では無い、犯人は映画に出るチャンスをものにしたが、それによって「顔」がバレることが心配なのだ。 小説作品で登場する題名は、清張の独創の産物なのだろうが、「利根の朝霧」は、1934年松竹の作品にあるようだ。 以下、登場作品は 「遠くからの声」 「溺れ谷」 「消滅」(絢爛たる流離/第十二話 「古本」(死の枝/第六話) 「不安な演奏」 「歪んだ複写」 「彩霧」 「お手玉」(隠花の飾り/第七話) 「泥炭地」 ほとんどが情景描写の中で、「映画館」・「映画監督」、映画見物などとして登場して、キーワードになるような登場の仕方では無い。 2024年11月21日 |
||||
| 【映画についての追記】 ●映画についての追記 【2024年12月21日】 清張と映画(映像)については、これまでもたくさん語られていると思う。 今回、『砂の器』の中に登場する映画について少し調べてみた。 映画の題名が、『砂の器』(監督:野村芳太郎)では「利根の朝霧」ですが、小説作品では「利根の風雲」です。 微妙に違うところが面白いのですが、「利根の朝霧」は、実在する映画のようです。 監督が野村芳亭。 野村芳亭は、野村芳太郎の父です。言わずと知れた、映画『砂の器』の監督です。 野村芳太郎がリスペクトして映画の中に忍び込ませたのでしょう。 ところが、他の映画「大江戸の鬼」「男の街」も実在するです。「北海の嵐」だけは見つかりませんでした。 ただ、ドキュメンタリーとして存在していた可能性があります。 「利根の朝霧」を野村芳太郎が忍び込ませたのではないかと推測しましたが、脚本家の橋本忍が「犯人」なのでは?
●野村芳太郎 野村芳太郎 - Wikipedia 野村 芳太郎 (のむら よしたろう、 1919年 (大正 8年) 4月23日 - 2005年 (平成 17年) 4月8日)とは、 日本 の 映画監督。 父は 野村芳亭。 父・芳亭は日本の映画監督の草分け的存在で、 松竹蒲田撮影所 の所長も務めた人物。 その関係で、京都と東京を行き来して育つ 。 京都市 生まれで、生後まもなく 東京市 浅草区 に移った 。 ●野村芳亭 松竹蒲田 所長野村芳亭の活躍(1922年頃) 蒲田の撮影所長だった野村芳亭は、勝見庸太郎主演の「清水次郎長」(1922)を監督している。 舞台的なものとは異なる映画的なスピーディな 動きとリアルな剣戟を見せようとし、宣伝でも「新時代劇」の文句が使われたという (時代劇なる呼称がもてはやされるようになったのは この頃からだという)。 上映にあたって、それまでのような蔭台詞や音曲鳴物に代わり、散文的な説明と和洋合奏の編曲を用いる新方式が取り入れられたと 言われている。また、清水次郎長は有名な侠客のため、仁侠映画のルーツと位置づけることも可能である。 野村は他にも、「地獄船」(1922)を監督している。チャールズ・チャップリンの「キッド」(1921)を、伊藤大輔が翻案・脚色した 人情喜劇作品である。新派劇団の重鎮で、松竹入社第1回主演作となる井上正夫が主人公の浮浪者を演じ、 少年役を子役の小藤田正一が演じている。 清張作品は、映画やテレビドラマなど今でも沢山映像化されています。 私のベストスリーを紹介して終わりにします。 ①『砂の器』 もはや小説とは別作品。独立した映画として楽しめます。 監督が野村芳太郎。脚本が橋本忍・山田洋次 ここで蛇足的研究の本領ですが、登場する俳優です。 加藤剛・加藤嘉・緒形拳・笠智衆・佐分利信。加藤は親子役ですし、何故が名前が一文字です。 (役者は一文字に限る/異論を認めず〈笑〉) ②『証言』(あるサラリーマンの証言) 脚本が橋本忍。清張作品での橋本忍脚本は秀逸である。監督は堀川弘道 小説作品もさることながら、脚本力の素晴らしさに唸らせられます。 作品出でてくる映画で「西部の嵐」は、西部の嵐 1936年 HOPALONG CASIDY RETURNS 別題:侠勇無双 (戦前) 映画西部劇 アメリカ B&W 54分 初公開日: 1951/01/ 公開情報:映配 実在する作品だった。 ③『張込み』 斬新な映像が、小説のテーマと合致して面白いです。 脚色が橋本忍。監督が野村芳太郎。 これ以外に、『点と線』『ゼロの焦点』『霧の旗』『霧の旗』『天城越え』などきりがない!!! ●「松本清張映像の世界(霧にかけた夢)」 霧プロが手がけた作品群の紹介もあり興味深い本でした。 2024年12月21日記 |
||||
| 【映画についての追記の追記】 ●映画についての追記の追記 【2025年1月21日】 映画「砂の器」上映50年(2024年12月23日:しんぶん赤旗の記事) 映画「砂の器」は、父と子の物語と言えます。原作とは多少趣が違うのですが、原作の一シーンを切り取り膨らませた映画は、原作者の清張に源作を超えたと言わしめた作品です。私は、清張原作の作品を映画化されたベスト3を「砂の器」・「証言」(あるサラリーマンの証言)・「張込み」を上げましたが、奇しくも今回の記事(赤旗/2024/12/23付)で清張自身も同様の指摘をしていたようです。 この3作品が、橋本忍の脚本である事は知っていましたが、改めて橋本忍の脚本の素晴らしさを実感しました。 映画評論家で、ノンフィクション作家の西村雄一郎氏の文章は、それを確認させてくれました。 西村雄一郎氏は、存じ上げていませんでしたが、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の記事で納得しました。 ※西村雄一郎 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 佐賀県の県都・佐賀市の老舗旅館「松川屋」の長男として生まれる。5歳の時、松竹映画『張込み』のロケ隊が実家の旅館に押し寄せてきた。 ロケ隊が1ヶ月も宿泊地として借りきったためであった。 特に刑事役の宮口精二から可愛がられた。小学校4年の時に黒澤明監督の『椿三十郎』に感銘を受けたのが、映画の世界をめざす契機となった。 2019年05月14日~15日 松本清張記念館友の会『春の文学散歩』 (2019年03月21日登録) ●Dの複合~東経135度線と丹後半島を巡る旅(1泊2日) (参加しました) ■橋本忍記念館にて購入■   2025年1月21日記 |
| 題名 | 「映画」 | 上段は登録検索キーワード |
| 書き出し約300文字 | ||
| 「砂の器」 | カメダ・亀嵩・ハンセン病・東北弁・方言・超音波・周波数・紙吹雪・前衛劇団・大臣・放浪・伊勢・映画 (伊勢・映画を追記) | |
| 第一章トリスバーの客 国電蒲田駅の近くだった。間口の狭いトリスバーが一軒、窓に灯を映していた。十一時過ぎの蒲田駅界隈は、普通の商店がほとんど戸を入れ、スズラン灯の灯りだけが残っている。これから少し先に行くと、食べもの屋の多い横丁になって、小さなバーが軒をならべているが、そのバーだけはぽつんと、そこから離れていた。場末のバーらしく、内部はお粗末だった。店にはいると、すぐにカウンターが長く伸びていて、申しわけ程度にボックスが二つ片隅に置かれてあった。だが、今は、そこにはだれも客は掛けてなく、カウンターの前に、サラリーマンらしい男が三人と、同じ社の事務員らしい女が一人、横に並んで肘を突いていた。客はこの店のなじみらしく、若いバーテンや店の女の子を前に、いっしょに話をはずませていた。レコードが絶えず鳴っていたが、ジャズや流行歌ばかりで、女の子たちは、ときどき、それに合わせて調子を取ったり、歌に口を合わせたりしていた。 | ||
| 「顔」 | 舞台俳優・五反田・殺人行・浜田駅・初花酒場・女給・いもぼう料理・映画・赤い森林・春雪・手紙・首実検・興信所 | |
| 井野良吉の日記 --日。今日、舞台稽古のあとで、幹部ばかりが残って何か相談をしていた。先に帰りかけると、Aと一緒になった。五反田の駅まで話ながら歩いた。「何を相談しているか知っているか」とAはぼくに云った。「知らない」「教えてやろう」と彼は話し出した。「今度、△△映画会社から、うちの劇団に映画出演の交渉があったんだ。例の巨匠族石井監督の新しい作品で、達者な傍役をうちの劇団から三、四人欲しいというのだ。マネージャーのYさんがこの間から映画会社に行ったり来たりして、忙しそうにしていたよ」「へえ、知らなかったな。それで、やるのかい?」とぼくは訊いた。「やるよ、勿論。劇団だって苦しいもの。ずっと赤字つづきだからな。Yさんの肝では、今度だけでなく、ずっと契約したらしい。先方さえよかったらね」 | ||
| 「証言」(黒い画集/第二話) 【あるサラリーマンの証言】 |
西大久保・丸の内・大森・渋谷・映画・偽証・筆跡・課長・陥穽(カンセイ)・愛人・若い恋人・最高裁 | |
| 女は、鏡に向かって化粧を直していた。小型の三面鏡は、石野貞一郎が先月買ってやったものである。その横にある洋服箪笥も、整理箪笥もそうである。ただ、デパートから買入れの時日だけが違っていた。部屋は四畳半二間だが、無駄のないように調度の配置がしてあった。若い女の色彩と雰囲気とが匂っている。四十八歳の石野貞一郎が、この部屋に外からはいってくるとたんに、いつも春風のように感じる花やかさであった。石野貞一郎の自宅はもっと大きくて広い。しかし、柔らかさがない。乾燥した空気が充満し調度は高価でも色あせて冷たい。家族の間に身を置いても、彼は自分の体温の中に閉じこもる姿勢になるのだ。家庭で目を開けていると、自分の心まで冷えてくるのである。石野貞一郎は洋服に手早く着替えて畳の上に身を横たえ片肘立てて煙草を喫っていた。目は女の化粧している後ろ姿を眺めている。梅谷千恵子は若い。着ているブラウスやスカートの色も、化粧の仕方も目のさめるような光をもっていた。 | ||
| 「お手玉」 (隠花の飾り/第七話) |
駒牟礼温泉・芸者・駆け落ち・別府・マッサージ・猟奇・京料理・角屋・心臓病・二階・梯子・板前・怪女 | |
| 東北地方に駒牟礼温泉がある。山裾に囲まれた狭い盆地で、芭蕉の「奥の細道」に出てくる川の上流にも沿っている。三つの県の県庁所在都市にわりあい近いのと、酒造と米の集散地で知られた都市に隣接しているから山間だが、歓楽郷である。そう遠くないところには奧州随一の名刹もあって、観光客の流れを吸収している。駒牟礼温泉ホテルと旅館が約四十軒ある。高層ホテルも六つあった。見番が二つあって芸者が総勢七十人ぐらいいる。川には擬宝珠のついた朱塗りの橋が三つ架かり、両岸の柳の並木道には雪洞が連らなり、旅館・料理屋・土産物店・小映画館・ストリップ劇場・バア・飲食店・ヌードスタジオなどがならぶ。高層ホテルは丘陵地にある。この町の住民の大半はなんらかのかたちで温泉の営業と関係を持つ。農家は少数で、夜の灯に生命を輝かす町である。 | ||
| 「古本」 (死の枝/第六話) |
東京の西・広島県府中市・古本屋・室町夜噺・栄華女人図・神田・女性雑誌・連載・鉄橋・月刊誌・随筆・批評家・刑事・謎解き | |
| 東京からずっと西に離れた土地に隠棲のような生活を送っている長府敦治のもとに、週刊誌のR誌が連載小説を頼みに来たのは、半分は偶然のようなものだった。長府敦治は、五十の半ばを越している作家である。若かった全盛時代には、婦人雑誌に家庭小説や恋愛小説を書いて読者を泣かせたものであった。まだテレビの無いころだったから、彼の小説はすぐに映画化され、それが彼の小説の評判をさらに煽った。長府敦治の名前は、映画会社にとっても雑誌社以上に偶像的であった。しかし、時代は変わった。新しい作家が次々と出て、長府敦治はいつの間にか取り残されてしまった。もはや、彼の感覚では婦人雑誌の読者の興味をつなぐことは出来なくなった。長府敦治の時代は二十年前に終わったといってもいい。ときどき短い読み物や随筆を書くことで、その名前が読者の記憶をつないでいる程度になった。 | ||
| 「消滅」 (絢爛たる流離/第十二話) |
別荘地・溶接工・蜜柑畑・融解・小説・ドストエフスキー・講義録・ガスバーナー | |
| 湘南地方のN都市は、最近、新しい別荘地帯としてとみに株を上げてきた。深く抉られた入江は、夏はヨット港になったし、冬は色づいた密柑山に囲まれて十分に暖かであった。つまり、避暑によく、避寒によかったので、誰かがここに目をつけ小さなコテージを建てた。誰かといっても無名の人間(たとえ金持ちであっても)ではブームにならない。それはジャーナリストが写真班を連れてくるような「著名人」でなければならなかった。映画監督でもいいし、歌手でもいいし、画家でもいいし、小説家でもよかった。俳優ならなおよかった。最初の開拓者がどのような職業であったかは問うところでない。とにかく、一群の有名人たちが別荘をここに持ったことでN地は急激にマスコミの脚光を浴びたのである。雑誌のグラビアには、高名な若い芸術家がヨットに半裸で乗り込んでくるところや、人気女優が海の上にさし出たベランダの上で嫣然としている姿など、きれいな調子で紹介された。 | ||
| 「遠くからの声」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 民子が津谷敏夫と結婚したのは、昭和二十五年の秋であった。仲人があって、お見合いをし、半年ばかり交際をつづけ、互いに愛情をもち会って一緒になった。愛情は民子の方がよけいに彼に傾斜したといえる。その交際の間、民子の妹の啓子は、時々、姉に利用された。民子の家庭は割合にきびしい方だったから、民子が敏夫と会うのに、そう何度も実行するのは気が引けた。その場合に啓子は利用された。一人で外出はいけないが、二人なら宥される。そのような家庭であった。民子と敏夫の会合は銀座へ出てお茶を飲んだり、食事をしたり、映画を見たり、そんな他愛のないものだったが回数の半分は啓子が必要であった。姉にとって邪魔な存在だったが、家を出るときには重宝だった。啓子は食事でも勝手な注文をつけ、映画も自分の好みを主張した。「利用の報酬としては当然の支払いよ」と云った。散歩するときでも姉たち二人を先にやるという心遣いは無く、いつも敏夫を真ん中にして並んで歩いた。啓子が居る限り、民子は敏夫と二人で居られるという意識の流れは寸分も無く、いつも啓子が対等に割り込んできた。その時、啓子は女子大を卒業する前の年であった。 | ||
| 「溺れ谷」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 早春の美しい朝、東京世田谷区上野毛にある山田千江子の家に青年が一人訊ねてきた。「竜田香具子さんはご在宅でしょうか?」女中に渡した名刺には「政経路線」編集部次長、大屋圭造としてある。背の高い男で、色は浅黒いが、大きな目が光を湛えていた。英国製の生地で仕立てた洋服を着ているから、ネクタイも、靴も、それに相当して贅沢だった。女中が、はい、と言ったのは、世間では山田千江子よりも滝田香具子の方が通っているからである。戦前の映画ファンなら、この名前を忘れることはあるまい。近代的な役柄で売り出し、数数の主演映画を撮ってきたスターである。今ではときどきテレビに脇役として出演し、往年のオールドファンを懐かしがらせている。訪問者の青年は、こぢんまりとした応接間に通された。洋間だが、一応、華やかな気分に装いがなされている。小さな調度一つ見ても、気の利いた工夫があった。だが、気をつけてみると、それがあまり高価な品でないことが分かる。つまり、豪華な意匠が凝らされてあるからである。 | ||
| 「不安な演奏」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 雑誌編集者の宮脇平助は、誰にも教えない自分の巣を三軒持っている。浅草に一件、池袋に一件、新宿に一件。どれも安バーであった。彼は芸能欄の担当である。仕事の上で映画人とのつき合いが多い。酒もかなり飲むし、遊びも好きだった。三十二歳で、こういう仕事をしていると、世の中が面白くてたまらない。彼はつき合いでいろいろキャバレーやバーに入ることはあるが、この三つの巣だけは絶対誰も連れて行かなかった。ここは彼にとって何の気がねもなしに大きな顔をして愉しめる場所だった。第一、自腹となれば、酒は安いのに限る。女の子もちょっと誘う気になれないような連中ばかりだから、思わぬ費用がかかることもない。映画担当だから、切符は自由になるし、それを女の子に二,三枚もくれてやれば、大もてだ。彼がスター級の裏話のあれこれを真偽とりまぜて話してやると、店の女は、瞳を輝かして聞き入っている。宮脇平助は、一件、無造作な格好をしているが、実は眼に見えぬところに彼の服装のお洒落があった。洋服にしても、ワイシャツにしても、飛びきり高いのだ。 | ||
| 「歪んだ複写」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 十一月の末の、寒い宵であった。六時前だが、完全に夜になっていて、東京の西の繁華街と言われるS地区には、銀座裏と同じくらいに賑やかな灯が輝き、人間の数はもっと多く流れていた。K通りは、近くに劇場や映画館が集まっていて、近所は、キャバレー、バー、ナイトクラブ、料理店といった店が、これも銀座裏と同じようにひしめいている。夜の遊び場であった。無論、広い地域なので殷盛さが平均しているという訳ではなかった。すこし横の通りにそれると、灯の稠密は少なくなり、人の歩きは疎らになる。が、その種類の店は、相変わらず多かった。ひとりの男が、人でも待っているような恰好で、その通りの或る地点に佇んでいた。寒い風のせいか、彼は片脚で貧乏ゆすりをしていた。近くのネオンの光が、男の顔を紅く浮かせるので分かったことだが、彼は三十前後の年齢にみえた。風の油気の無い髪と、古いオーバーの裾が煽られていた。使い過ぎたネクタイも結び目が細くなっているし、靴にも艶がない。要するに、安サラリーマンとしか踏めないのである。 | ||
| 「彩霧」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 午後四時半に銀行を出た。なま暖かい早春の土曜日であった。スモッグで朝から太陽が白く濁っている。いつもは六時過ぎまで残るのだが、今日は営業が午前中の上、出納との帳尻もいつもより早く合った。安川信吾は使い古した黒皮の手提鞄を面倒臭そうに持っている。映画館に入り、二時間かかって外に出ると食事を摂った。百円のチキンライス。八時近くになっていた。ふらりと街を歩く。少し重そうな鞄であった。有楽町界隈は、人で混み合っている。彼は銀行マンらしく調髪には気をつけるほうである。二十八歳。ぶらぶらと歩いて洋品店に入った。下着が一通りと、セーターと替ズボンを一つずつ買った。ついでにスーツケースを求めて、買った品をその中に突込み、総計八千円を払った。財布の中は残り少なくなっている。二つの荷物を両手に提げてタクシーに乗り、東京駅前の小さな果物屋に入った。横では稲荷ずしや巻きずしを売っている。汚い店だ。 | ||
| 「泥炭地」 | ※まだ紹介作品ではない | |
| 河東電気小倉出張所は、倒産した大きな料理屋のあとに入っていた。すぐ裏が遊郭、前の通りに劇場と映画館とがあり、小料理店がならび、近くには検番がった。昭和二年の三月、小学校高等科を出た福田平吉が職業紹介所から渡された一枚の紙で配属されたのはこの河東電気小倉出張所であった。職業紹介所の窓口の係員は平吉の貧弱な身体つきを見て、力仕事はできそうもないから住みこみの丁稚奉公はどうか、と付き添ってきた父の丈太郎にきいた。丈太郎は首を振り、この子は一人息子ですけん住み込みはとても無理ですといった。平吉は丈太郎の三十六のときの子である。 | ||