| ●里子に出された峯太郎は...父の経歴 |
⑦■「夜が怕い」
(1990年(平成3年):月刊文藝春秋2月号 |
⑥■「骨壺の風景」(自叙伝的作品)
(1980年(昭和55年):新潮1月号 |
⑤■「碑の砂」(エッセイ)
(1970年(昭和45年):潮1月号 |
●夜が怕い
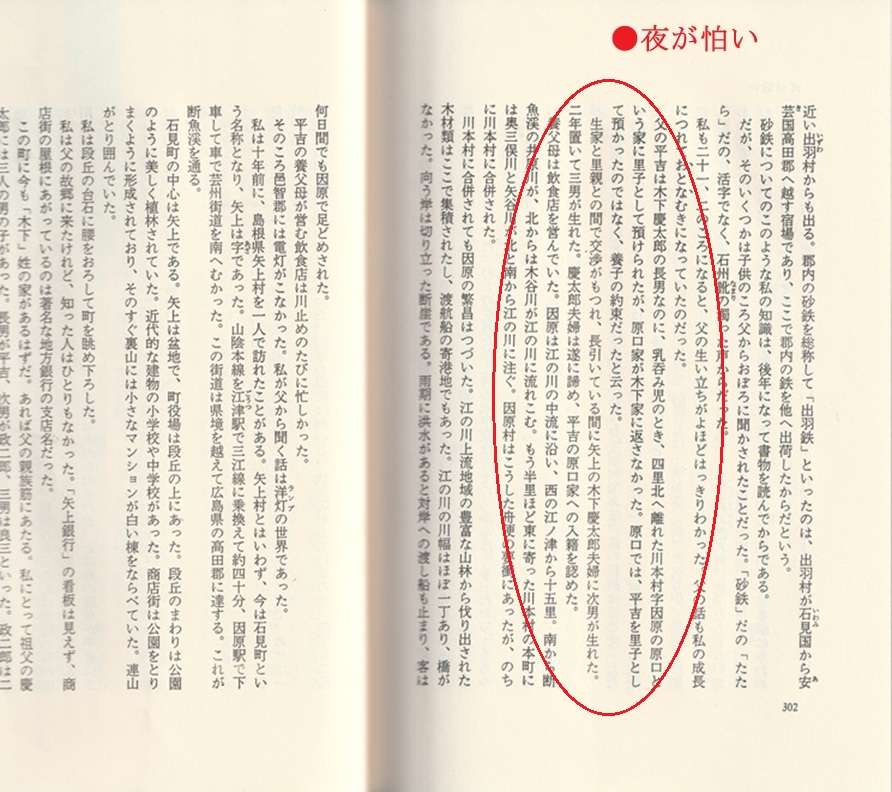
※『夜が怕い』(【草の径】の304P)
|
●骨壺の風景
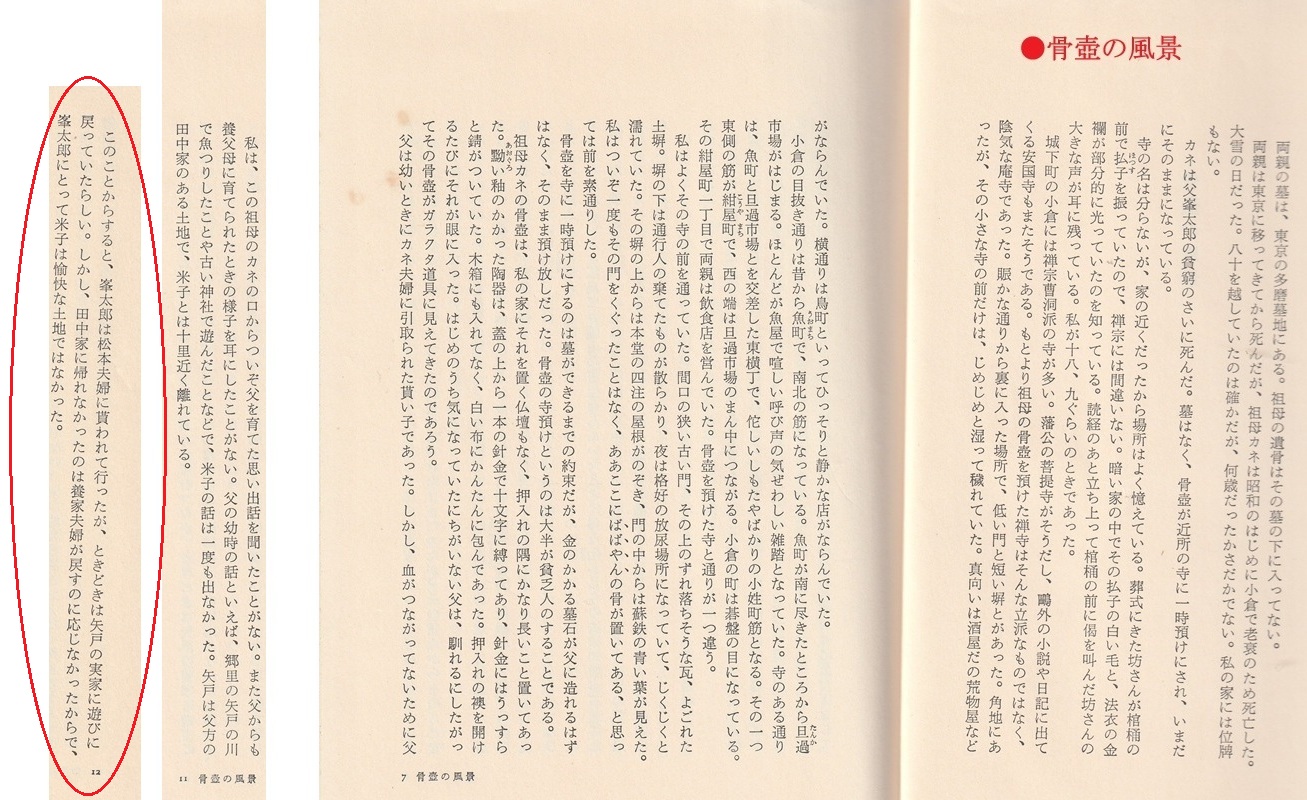
※『骨壺の風景』(【岸田劉生晩景】の6・7・11・12P)
|
●碑の砂
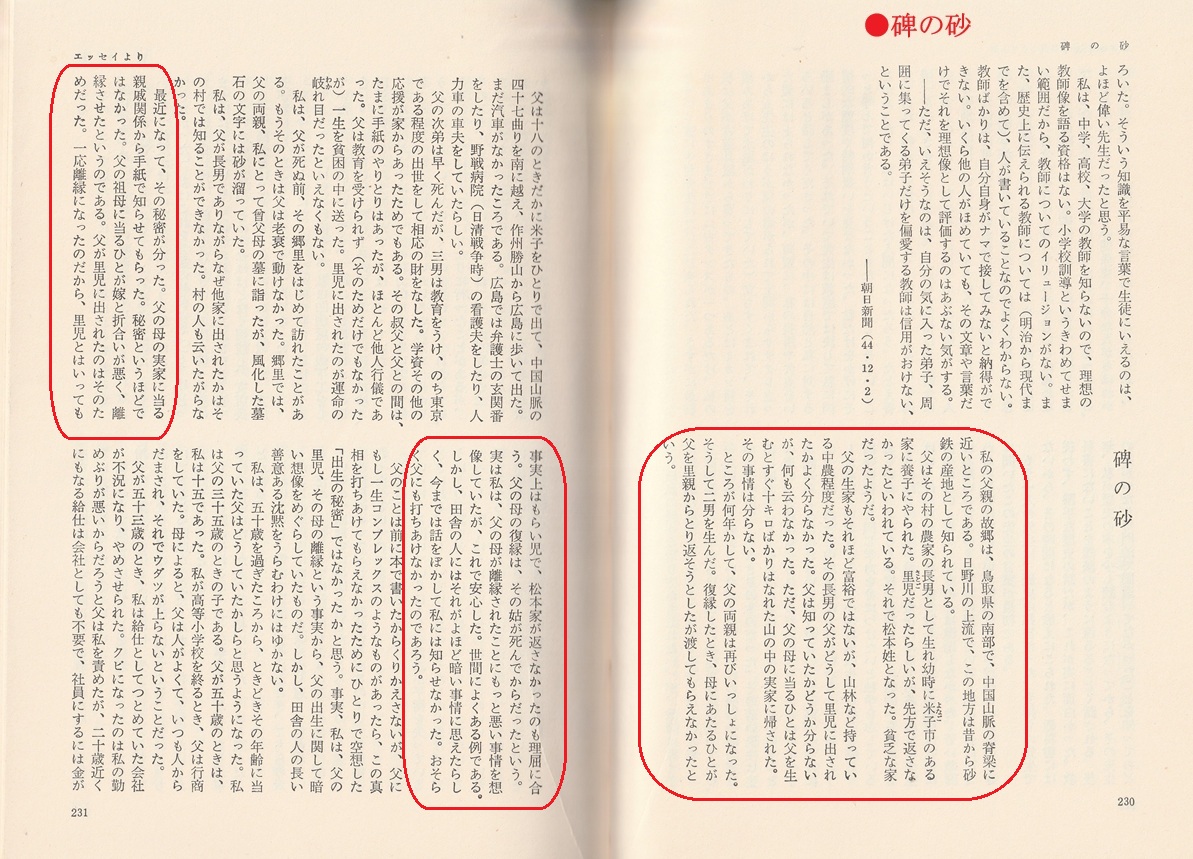
※『碑の砂』(【松本清張全集34】の230・231P)
|
●主人公である「私」(清張?)の思い出話として綴られている。
私は、作品内容に直接関係ないと思った。
直接関係ないだけでなく、間接的にも関係ないと感じられた。
残念だが、納得のいかない挿話。 |
●自叙伝的作品である。父(峯太郎)の養父の名前が健吉とされているが、米吉が正確のようだ。
清張一家の小倉や下関の壇ノ浦での生活がリアルに描かれている。
貧乏のどん底がこれでもかと描写されている。
「半生の記」より、自叙伝的だ。 |
●エッセイですが、半生の記以上に真実が語られているように感じます。
父の出生の秘密が、清張の心の奥底に沈殿していたのではと思います。
秘密が、親戚関係からの手紙で明らかになるのですが、私には納得していなかったとも読めました。その結果が、最晩年になっても心の焔となって「夜が怕い」として書かざるを得なかったのではと思慮しました。 |
|
④■「暗線」
(1963年(昭和38年):サンデー毎日6月 |
③■「半生の記」(自叙伝)
(1963年(昭和38年):文藝1月号 |
②■「田舎医師」(影の車:第六話)
(1961年(昭和36年):婦人公論6月号 |
●暗線
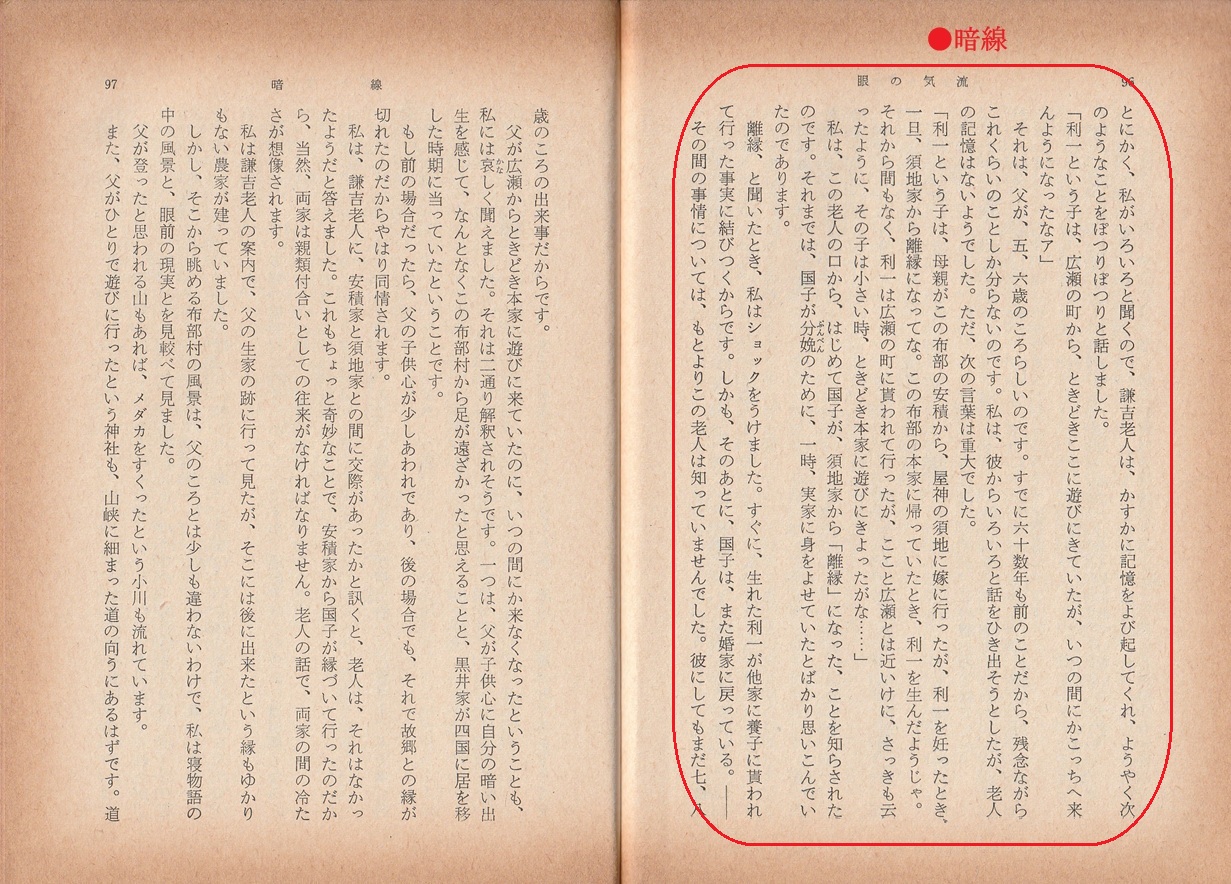
※『暗線』(【眼の気流】の96P)
|
●半生の記
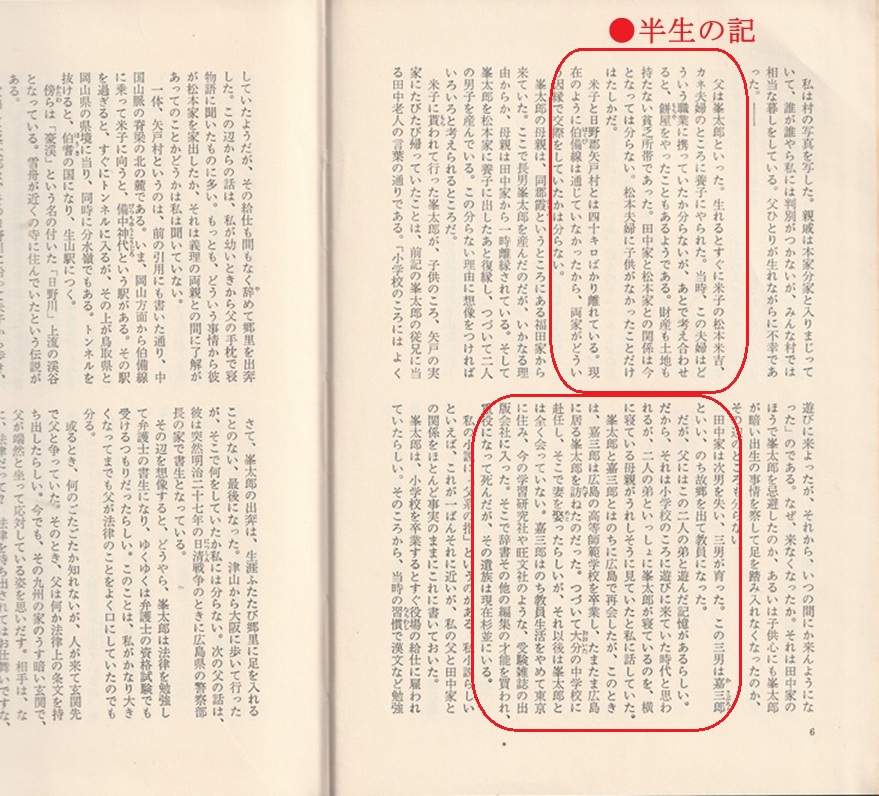
【「半生の記」と自叙伝について】(自叙伝)
※『半生の記』(【松本清張全集34】の6P)
|
●田舎医師
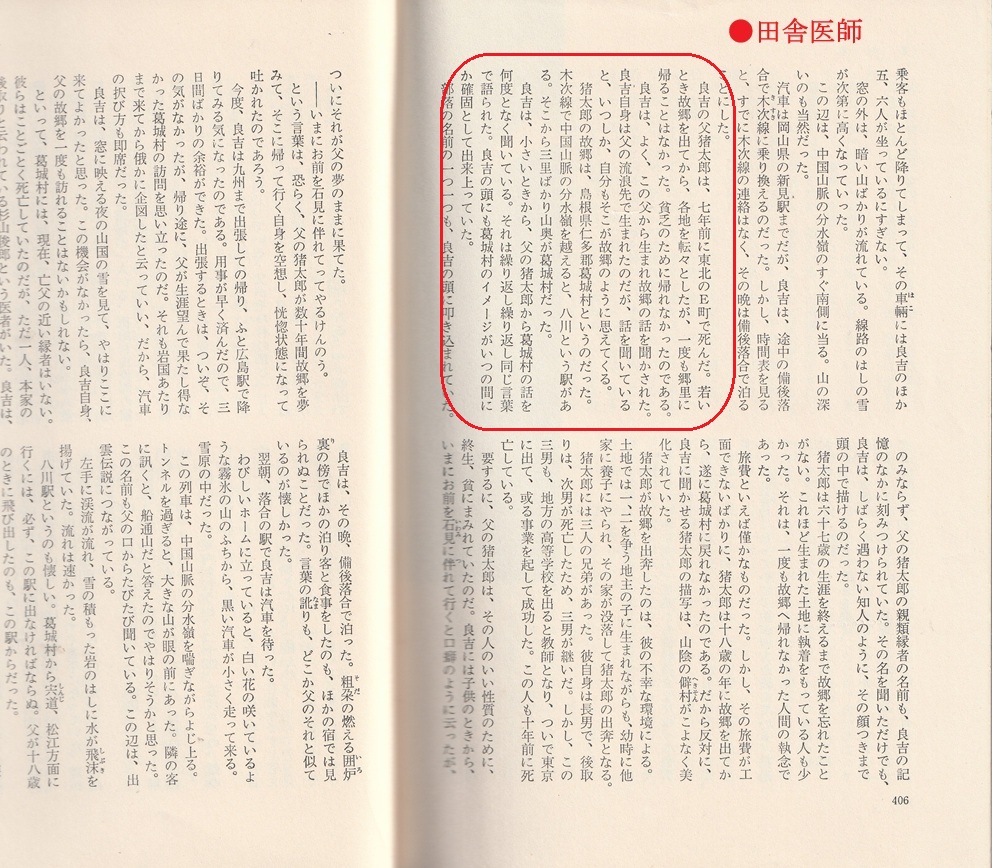
※『田舎医師』(【松本清張全集1】の406P)
|
●黒井利一(松本峯太郎)が養子(里子)に出された事情が詳しく記述されている。
清張は、新聞記者として「私」で登場。
父の経歴を詳しく聞くことになるが、父(利一/峯太郎)の出生の秘密が隠されている。
「悪い事情」として、清張の心の奥にわだかまりとして残っているようだ。
一応、エッセイの「碑の砂」で解決している。 |
●自叙伝。真実が語られているのでしょう。
登場人物
松本米吉(峯太郎の養父)
松本カネ(峯太郎の養母)
松本峯太郎(清張の父)
松本タニ(清張の母/峯太郎の妻)
タニは、広島の農家の生まれ。
字が読めなかった。(一丁字がなかった) |
●登場人物で、杉山良吉=松本清張
杉山猪太郎=松本峯太郎
猪太郎は、杉山家の養子になるのだが、実家の姓が不明確で、すべて杉山姓で描かれている。
設定が他の作品と少し違うようだ。
(読み込み不足かもしれない?) |
|
①■「父系の指」 (自叙伝的作品)
(1955年(昭和30年):新潮9月号 |
1955年9月に最初の「父系の指」が発表され、以後
1961年6月「田舎医師」
1963年1月「半生の記」
1963年6月「暗線」
1970年1月「碑の砂」
1980年1月「骨壺の風景」
1990年2月「夜が怕い」
と、発表されている。
46歳から82歳に及ぶ、清張にとっては父の経歴は永遠のテーマだったと思われる。
83歳で死亡しているのだから、恐ろしい執念と言える。
最晩年の作品で或る【草の径】(シリーズ作品)での「夜が怕い」は、【草の径】で読んだ詩の一節が
記されているが、心に残る。
『わが力なきをあきらめしが、されど草の葉で綴る焔文様』
父峯太郎の生涯は清張にとって「焔文様」なのだ!
|
●父系の指
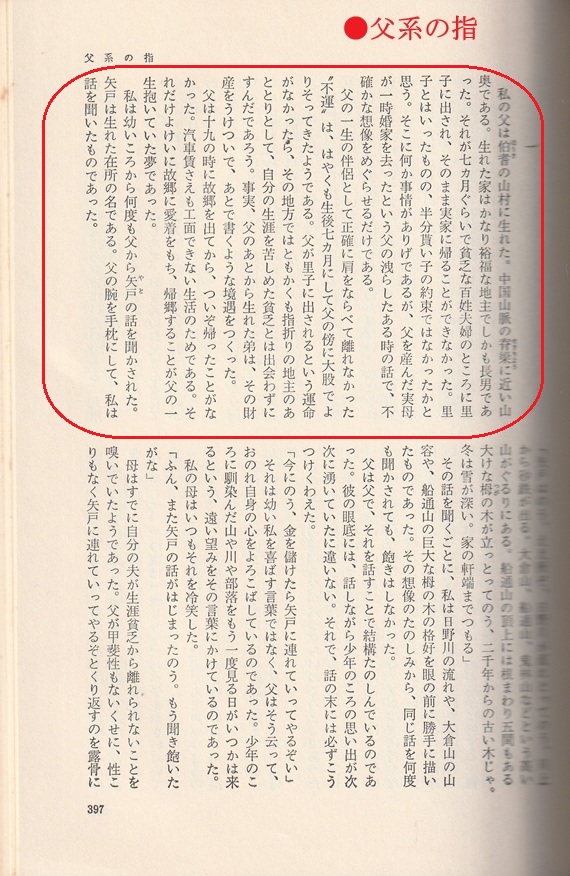
※『父系の指』(【松本清張全集35】の397P)
|
●清張の父峯太郎が最初に登場する作品です。
登場人物は実名が殆どです。
後に書かれる、「骨壺の風景」と同じく、自叙伝的作品と呼べるのではないでしょうか?
峯太郎の出生の秘密が問題提起されていると思います。
「半生の記」の中で、「父系の指」がいちばん事実に近いと書いている。 |
全くの余談だが、私は、清張の父(峯太郎)の出生の秘密に大変興味を持ちました。
私の父の経歴が複雑で、共通性を読み取ったからです。
(実は、複雑さを感じたのは、数年前です。)
戸籍謄本を取り寄せ、家系を調べました。驚きの連続でした。まさに事実は小説より奇なりです。文章を書く事など全くの門外漢でありながら書き残したい衝動に駆られたのです。自分なりにまとめた文章を兄弟に送りました。反応は様々でしたが、誰かに話したい衝動から、このホームページに『実録・家系図』を書き始めました。
文学的才能は全くないので、幼稚で稚拙な文章ですが話の内容は、清張の父(峯太郎)の経歴に負けないと思っています。(笑)
『実録・家系図』を読んで下されば幸いです。 |
 徹底検証シリーズ No09
徹底検証シリーズ No09
