
![]() 疑問
疑問
▼ページの最後▼
| 疑問 蛇足的疑問 『シリーズ作品と単行本・【草の径】に関連して』 |
疑問のMENU |
|||||||||
| シリーズ作品として直ぐ思いつくのは、「昭和史発掘」・「日本の黒い霧」・「現代官僚論」ドキュメント物などで、小説では、「隠花の飾り」・ 「影の車」・「黒の図説」・「死の枝」や「絢爛たる流離」・「大奥婦女記」などが上げられ【シリーズ作品検索】で網羅的に紹介している。 個別に考察してみても特徴的なことは分からないが、ここに改めて取り上げた【草の径】は、作品を紹介していく中で幾つかの疑問に突き当たりました。発表された順に、その経緯を見てみます。 ※①月刊文藝春秋⇒②【草の径】(単行本/1991年8月)⇒③松本清張全集66(1996年3月:左から右の順で出版されています。
清張の作品は、最初から単行本として出版されるのが極端に少ない。ほとんどが、週刊誌や月刊誌で発表され、後に単行本として出版されることが多い。「書き下ろし」としては、「黒血の旋舞」くらいしか思い浮かばない。 シリーズ作品だから、短編の集合で、作品には、それなりの関連性ありそうだが、改めてみるとそうでもない。 【絢爛たる流離】のように、ある意味続き物で、登場人物も連続して登場する。この作品はむしろ特別である。 短編だけではない。長編もシリーズ作品として登場する。(【歌のない歌集】・【禁忌の連歌】・【黒の線刻画】/中編も含む) 【別冊黒い画集】は、ほとんど中編の作品です。 統一性がありません。 このテーマで書き始めた時は、シリーズ作品は、単行本で出版する時、タイトルを決めたのではないかと思っていた。 実態は、タイトルを決めて、シリーズ作品としてまとめている。 紛らわしかったのは、【草の径】は、月刊文藝春秋に連載が始まったのだが、1月から「削除の復元」がスタートしている。 この作品を、シリーズ作品の第一話と早とちりしていた。(このホームページでも、そのように取り扱っていた:訂正した) 実際はシリーズ作品は、4月から始まった「ネッカー川の影」が、第一話だった。 最初から、シリーズ作品と銘打って連載が始まる場合は、当然シリーズ作品名発表されている、【草の径】は、最初からシリーズ作品としてテーマも決まっているらしく、そのための取材旅行もしている。 取材日記が残されていた。松本清張研「第三号(2002年)」に、掲載されている。(ヨーロッパ『草の径』取材日記) 取材旅行は海外で、「ネッカー川の影」・「モーツアルトの伯楽」に結実しているようだ。 ただ、③松本清張全集66(1996年3月30日出版)で順番が変わっている。清張の死亡後の出版なので、清張の考え方とは思えない。 だったら、何の為の順番変更なのだろうか? シリーズ作品で、全ての作品の紹介が終わった場合、「作品紹介完結に当たって」で、それぞれの疑問を書いている。 参考にしていただきたい。(「作品紹介完結に当たって」の例:【影の車】) 精査した訳ではないが、「週刊朝日」に多くの連載がなされ、シリーズ作品が登場する。 【黒の図説】・【黒い画集】・【黒の様式】 感覚的には「週刊朝日」が多いと思っていたが、特別多い訳ではないようだ。 月刊誌では、【隠花の飾り】【死の枝】(小説新潮)・【影の車】【絢爛たる流離】(婦人公論)・【彩色江戸切り絵図】【私説・日本合戦譚】(オール讀物) 【紅刷り江戸噂】(小説現代)新潮) シリーズ作品は、名前もそれらしいものが多い。連作を想像することができる。【絢爛たる流離】・【黒い画集】や【死の枝】は、代表的な 作品と言える。 しかし、【草の径】は、その名からは想像も付かない。作品の内容も多彩であり、統一性が感じられない。取材旅行の成果と言うべき作品が登場しているが、一部にすぎない。 むしろ、シリーズ作品としてのタイトルが、小説のタイトルではないかと思えるものさえある。 【影の車】・【隠花の飾り】・【黒の線刻画】は、意味深なタイトルとして通用すると思う。 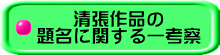 と と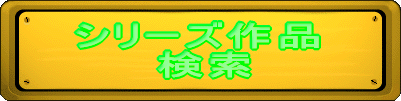 が、参考になると思う。 が、参考になると思う。2025年08月21日登録 |
||||||||||