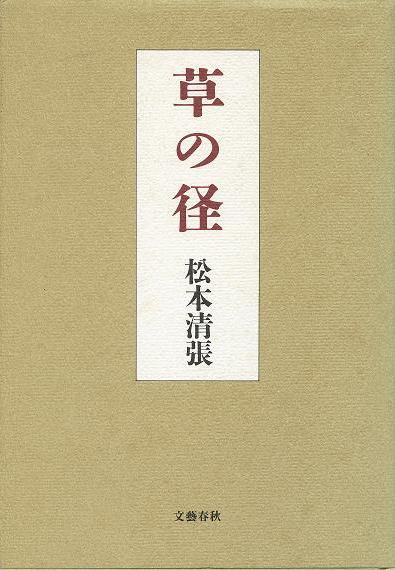研究作品 No_169 【モーツアルトの伯楽】 (月刊文藝春秋での発表時には、五回(1990年8月号) ※単行本【草の径】では第四話として集録・全集では二話として集録 〔月刊 文藝春秋〕 1990年(平成02年)8月号 |
|||
| 午前十時、日本人の女がタクシーでブルク劇場近くのホテルに男を迎えに来た。男は東京から来た旅行者である。片手にコートを抱え、もう一方の肩にベルトのついた重たげなカバンのようなものをさげていた。二人は昨夜シュヴェヒャー空港で初めて顔をあわせた。彼が一ヵ月前に東京の旅行社に対して申し込んだ通訳の希望は、ウィーンに長く住んでいる日本女性で市内の地理にあかるい人というのだ。旅行社からの回答は、ウィーンに十年以上住んでいて、在留邦人にはドイツ語を、オーストリア人にはイタリア語を教えているというのだった。ウィーンでイタリア語を習っているのはたいてい音楽家のタマゴで、オペラ歌手を志している手合いかもしれないと男は思った。十一月の初めで、空は黒い雲がまだらに濁って、いまにも雨が降りそうであった。寒かった。タクシーの座席に女を先に乗せた男は、肩からベルトをはずして、鼠色のズックに包んだものを膝の上に置いて抱いた。タクシーは夕方までの約束でチャーターしていた。 |
|||
| シリーズ作品「草の径」は、清張最晩年の作品です。 発表時から単行本に収録されるまでに紆余曲折があったように見受けられる。 発表は、「月刊 文藝春秋」で、1990年(平成2年)1月号から始まっている。 1990年(平成2年)1月号=「削除の復元」 1990年(平成2年)4月号=「ネッカー川の影」 1990年(平成2年)5月号=「死者の網膜犯人像」(原題:死者の眼の犯人像) 1990年(平成2年)6月号=「「隠り人」日記抄」 1990年(平成2年)8月号=「モーツアルトの伯楽」 1990年(平成2年)10月号=「呪術の渦巻き文様」(原題:無限の渦巻き文様) 1990年(平成2年)12月号〜1991年(平成3年)1月号=「老公」 1991年(平成3年)2月号=「夜が怖い」 何れも短編であるが、以上の通り順次発表されている。(必ずしも毎月発表された訳では無いようだ) ●シリーズ作品【草の径】として単行本で出版 1991年に文藝春秋社から単行本「草の径」が、出版されている。(私は3版を蔵書/初版は1991年)
●全集の第66巻(1996年(平成8年)3月30日/初版) ※「松本清張全集 66 老公 短篇6」では、「削除の復元」は、 シリーズ「草の径」ではなく単独で収録 全集66巻短編6では、「草の径」 収録順番がかなり違っている。 それぞれ出版事情があるのだろうが、「老公」が、草の径の第一話のように編集されていて 「削除の復元」が、単独の短編として編集されている。奇妙に感じられる。 収録内容は 一.【草の径】(siri-zu03) 1.老公(077__02) 2.モーツアルトの伯楽(075__02) 3.死者の網膜犯人像(073__02) 4.ネッカー川の影(072__02) 5.「隠り人」日記抄(074__02) 6.呪術の渦巻文様(076__02) 7.夜が怕い(078__03) 二.「河西電気出張所」(613__03) 三.「山峡の湯村」(046__02) 四.「夏島」(606___02) 五.「式場の微笑」(113__02) 六.「骨壺の風景」(058__02) 七.「不運な名前」(614__02) 八.「疑惑」(004__02) 九.「断崖」(609__02) 十.「思託と元開」(704) 十一.「信号」(607__02) 十二.「老十九年の推歩」(608__02) 十三.「泥炭地」(677__02) 十四.「削除の復元(071) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 場所はウイーンのようだ。 「草の径」の第一話「ネッカー川の影」がドイツだったので、当時清張はヨーロッパへ取材旅行へ行っていたようなので それらの成果が、「草の径」に結びついているのだろう。 清張の略歴を見ると、1990年にはイギリス・ドイツに取材旅行に行っている。
ウイーンを舞台に男女の話なのだろうか? −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●「伯楽」について 秦の穆公に仕えた。馬の育成に功労があったため、星宿の一つで天馬を管理する神仙であるという「伯楽」にちなんで「伯楽将軍」の 名を与えられた。著書に『伯楽相馬経』などがある。 馬が良馬か否かを見抜く技術(相馬眼、相馬術、目利き術)に優れていた。また、調教師や獣医としての技術ももっていた。 後世の東アジアにおいては、これらの技術の達人の代名詞として「伯楽」の名前が用いられる。 例えば、『韓非子』などの諸子百家では、主に喩え話における喩えとして伯楽の名前や逸話が頻繁に言及される。 または、唐代の韓愈『雑説』に由来することわざ「世に伯楽あり、しかる後に千里の馬あり(世有伯楽,然後有千里馬)」 「千里の馬は常にあれども伯楽は常にはあらず」などでも知られる。 現代のスポーツ、コーチング、教育全般において、後進の育成に優れた指導者のことを「名伯楽」と呼ぶこともある。 ●ウイーン 第一次世界大戦までは、オーストリア=ハンガリー帝国の首都として、ドイツ帝国を除く中東欧の大部分に君臨し、 さらに19世紀後半までは神聖ローマ帝国やドイツ連邦を通じて、形式上はドイツ民族全体の帝都でもあった。 クラシック音楽が盛んで、過去にモーツァルトやベートーヴェン、シューベルトなど、多くの作曲家が活躍したことから 「音楽の都」・「楽都」とも呼ばれる。 |